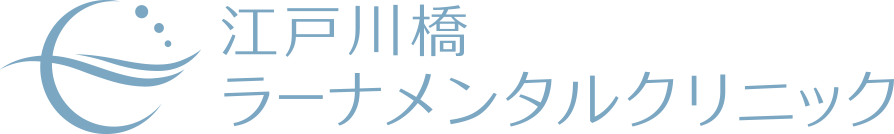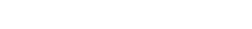- 記事の要点
- ADHD(注意欠如・多動症)とは
- ADHDの主な症状と特徴:こころとからだの変化
- ADHDの原因として考えられていること
- ADHD(注意欠如・多動症)はどのくらいの人が経験するのか
- ADHD(注意欠如・多動症)の診断
- ADHD(注意欠如・多動症)の治療法と回復への道のり
- ADHD(注意欠如・多動症)のまとめ
記事の要点
- ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」を特徴とする、生まれつきの脳機能の特性です。
- 症状は子どもの頃から見られ、日常生活に困難が生じますが、決して本人の性格や努力不足が原因ではありません。
- 適切な治療(薬物療法やカウンセリング)と環境の工夫により、症状とうまく付き合い、あなたらしい生活を送ることが可能です。
ADHDは、Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder の略です。日本語では、「注意欠如・多動症」または「注意欠如・多動性障害」、「注意欠陥多動障害」などと訳されます。
ADHD(注意欠如・多動症)
とは
 ADHDは、Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder の略で、日本では「注意欠如・多動症」と呼ばれ、かつては「注意欠陥・多動性障害」という名称も使われていました。
ADHDは、Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder の略で、日本では「注意欠如・多動症」と呼ばれ、かつては「注意欠陥・多動性障害」という名称も使われていました。
ADHDは、不注意、多動性、衝動性を主な特徴とする発達障害の一つであり、「性格の問題」や「甘え」ではありません。適切な理解と支援があれば、その特性とうまく付き合いながら、生活を送ることも期待できます。
ADHDの主な症状と特徴:
こころとからだの変化
ADHDの症状は、大きく分けて「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特徴があります。これらの症状は、小学生の頃から目立ち始めることが多く、大人になっても続きます。ただし、すべての方に3つの特徴がすべて現れるわけではなく、不注意が目立つタイプ、多動性・衝動性が目立つタイプ、両方が混在するタイプがあります。
不注意の症状
不注意の症状として、細かいことに注意を払うのが苦手で、仕事や勉強でケアレスミスが多くなることがあります。また、一つのことに集中し続けることが難しく、すぐに気が散ってしまいます。話を聞いているときも、別のことを考えてしまい、相手の話の内容を忘れてしまうことがあります。
- 仕事や勉強で、ケアレスミス(不注意な間違い)が多い。
- 課題や作業に集中し続けることが難しく、すぐに飽きてしまう。
- 話しかけられても、上の空で聞いていないように見えることがある。
- 指示されたことを最後までやり遂げられない。
- 作業や活動を順序立てて行うことが苦手(例:段取りが悪い)。
- 精神的な努力が必要な課題(例:書類作成、長文を読むこと)を避けがち。
- 財布や鍵、携帯電話など、大切なものを頻繁になくしたり、置き忘れたりする。
- 外部の刺激にすぐに気が散ってしまう。
- 約束ややるべきことを忘れがち。
日常生活では、物をなくしやすい、約束を忘れやすい、締め切りに間に合わないといった困難が生じることがあります。部屋の片付けや書類の整理が苦手で、必要なものがすぐに見つからないという経験をお持ちの方も多いでしょう。これらは決して「だらしない」からではなく、脳の注意機能の特性によるものです。
多動性・衝動性の症状
 多動性の症状は、じっとしていることが苦手で、常に体のどこかを動かしていたくなる特徴です。大人になると、外見上の多動は目立たなくなることが多いですが、内面的な落ち着きのなさは続きます。会議中に貧乏ゆすりをしたり、長時間座っていることが苦痛に感じたりすることがあります。
多動性の症状は、じっとしていることが苦手で、常に体のどこかを動かしていたくなる特徴です。大人になると、外見上の多動は目立たなくなることが多いですが、内面的な落ち着きのなさは続きます。会議中に貧乏ゆすりをしたり、長時間座っていることが苦痛に感じたりすることがあります。
衝動性の症状としては、思いついたことをすぐに口に出してしまったり、順番を待つことが苦手だったりします。買い物で衝動買いをしてしまう、相手の話を最後まで聞かずに話し始めてしまうといった行動も、この特性によるものです。感情のコントロールが難しく、些細なことでイライラしたり、落ち込んだりすることもあります。
- 手足をそわそわ動かしたり、貧乏ゆすりをしたりと、じっとしていられない。
- 会議中など、座っているべき場面で席を離れてしまうことがある。
- (子どもの場合)不適切な場所で走り回ったり、高い所に登ったりする。
- 静かに過ごすことが苦手。
- まるで「エンジンで動かされているように」常に活動しているように見える。
- しゃべりすぎることが多い。
- 相手が話し終わる前に、さえぎって話し始めてしまう。
- 順番を待つことが苦手。
- 他の人の会話や活動に、割り込んでしまうことがある。
日常生活への影響
これらの症状により、仕事や学業、人間関係などさまざまな場面で困難を感じることがあります。締め切りに追われたり、複数の仕事を同時にこなすことが求められたりする現代社会では、特に苦労を感じやすいかもしれません。しかし、ADHDの特性には、創造性の高さ、行動力、新しいことへの好奇心といった強みもあります。自分の特性を理解し、適切な工夫や環境調整を行うことで、これらの強みを活かしながら生活することができます。
ADHDの原因として
考えられていること
ADHDの原因は、単一のものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って生じると考えられています。現在の医学研究では、主に生物学的な要因が注目されていますが、心理的・環境的な要因も症状の現れ方に影響を与えることが分かっています。
脳の機能的な特性として、前頭前野(ぜんとうぜんや)と呼ばれる脳の前方部分の働きが、ADHDの症状と関連していることが明らかになっています。この部分は、注意の制御、行動の抑制、計画立案などを担っており、ADHDの方では、この領域の活動パターンが異なることが脳画像研究で示されています。また、ドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスも関係していると考えられています。
遺伝的な要因も重要で、家族にADHDの方がいる場合、その可能性が高くなることが知られています。ただし、これは「必ず遺伝する」という意味ではなく、あくまで可能性の話です。
ADHD(注意欠如・多動症)
はどのくらいの人が
経験するのか
ADHDは、決して珍しいものではありません。世界的な統計では、子どもの約5%、成人では約2.5%に認められると報告されています。これは、クラスに1〜2人、あるいは40人の職場に1人はADHDの特性を持つ方がいる計算になります。
子どもの頃は「多動性」が目立つため男の子に診断がつきやすい傾向がありますが、大人になるとその差は縮まります。女性の場合は、多動性が目立たず「不注意」が中心であることも多く、子どもの頃には見過ごされ、「物静かだけど、どこか抜けている子」といった印象を持たれ、大人になってから仕事や家事・育児などで困難が表面化し、初めてADHDと診断されるケースも少なくありません。
ADHD(注意欠如・多動症)の診断
診断の際には、国際的な診断基準であるDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)やICD-11(国際疾病分類第11版)が用いられます。DSM-5-TRでは、不注意症状9項目、多動性・衝動性症状9項目のうち、それぞれ6項目以上(17歳以上では5項目以上)が該当し、それらの症状が12歳以前から存在し、複数の場面で機能障害を引き起こしていることが診断の条件となります。
DSM-5-TRにおけるADHDの診断基準(概要)
DSM-5-TRでは、以下の「不注意」と「多動性および衝動性」の症状が、それぞれ9項目ずつ挙げられています。
- 不注意(以下の症状のうち6つ(17歳以上は5つ)以上が6ヶ月以上持続し、発達の水準に不相応で、社会的および学業的/職業的活動に直接悪影響を及ぼしている)
- 学業、仕事、またはその他の活動において、綿密に注意することができない、または不注意な過ちをおかす。
- 課題または遊びの活動中に注意を持続することが困難である。
- 直接話しかけられたときに聞いていないように見える。
- 指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動または指示を理解できないためではない)。
- 課題や活動を順序立てることが困難である。
- 精神的努力の持続を要する課題(学業や宿題など)に従事することを避ける、嫌う、またはいやいや行う。
- 課題や活動に必要な物をしばしばなくす(例:おもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具)。
- 外部からの刺激によって容易に注意をそらされる。
- 日々の活動において忘れっぽい。
- 多動性および衝動性(以下の症状のうち6つ(17歳以上は5つ)以上が6ヶ月以上持続し、発達の水準に不相応で、社会的および学業的/職業的活動に直接悪影響を及ぼしている)
- 手足をそわそわと動かしたり、もじもじしたりする。
- 教室や、その他座っているべき状況で席を離れる。
- 不適切な状況で走り回ったり高い所に登ったりする(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。
- 静かに遊んだり余暇活動につくことができない。
- “じっとしていられない”またはまるで“エンジンで動かされるように”行動する。
- しゃべりすぎる。
- 質問が終わる前にだしぬけに答え始めてしまう。
- 順番を待つことが困難である。
- 他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする(例:会話やゲームに割り込む)。
さらに、以下の条件を満たす必要があります。
- 不注意または多動性・衝動性の症状のいくつかが12歳になる前から存在していた。
- 不注意または多動性・衝動性の症状のいくつかが2つ以上の状況(例:家庭、学校または職場;友人や親戚といるとき;その他の活動において)で存在する。
- これらの症状が、社会的、学業的、または職業的機能を損なっている、またはその質を低下させているという明確な証拠がある。
- これらの症状は、精神病性障害の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患(例:気分障害、不安障害、解離性障害、パーソナリティ障害、物質中毒または離脱)ではうまく説明されない。
診断プロセスの実際
 初診では、現在の症状だけでなく、子どもの頃からの成育歴、学校での様子、家族歴なども詳しく聞かれます。可能であれば、通知表や母子手帳など、過去の記録を持参すると診断の参考になります。また、家族や親しい人からの情報も重要で、本人が気づいていない症状について、周囲の視点から情報を得ることもあります。
初診では、現在の症状だけでなく、子どもの頃からの成育歴、学校での様子、家族歴なども詳しく聞かれます。可能であれば、通知表や母子手帳など、過去の記録を持参すると診断の参考になります。また、家族や親しい人からの情報も重要で、本人が気づいていない症状について、周囲の視点から情報を得ることもあります。
心理検査も診断の補助として用いられることがあります。知能検査で全体的な認知機能を評価したり、注意機能や実行機能を測定する検査を行ったりします。これらの検査は、ADHDの診断そのものというより、個人の認知特性を詳しく把握し、より適切な支援方法を検討するために行われます。
他の疾患との鑑別
うつ病、双極性障害、不安障害など、他の精神疾患でも集中力の低下や落ち着きのなさが現れることがあるため、これらとの鑑別も重要です。また、ADHDの方は、これらの疾患を併発することも多いため、総合的な評価が必要となります。
自己判断でADHDと決めつけることは避け、気になる症状がある場合は、早めに専門機関に相談することをお勧めします。診断を受けることで、自分の特性を正しく理解し、適切な対処法を見つけることができます。「診断を受けること=レッテルを貼られること」ではなく、「自分らしく生きるための第一歩」と考えていただければと思います。
ADHD(注意欠如・多動症)
の治療法と回復への道のり
ADHDの治療の目標は、特性を「なくす」ことではなく、症状によって生じる困難を減らし、ご自身の特性を理解し、長所を活かしながら、より快適な日常生活を送れるようにすることです。
治療は、ご本人の希望や症状の程度に合わせて、以下の方法を組み合わせて行われます。
心理社会的治療と環境調整
「自分に合った工夫や環境を見つける」ことが治療の基本となります。
心理教育
まず、ご自身のADHDという特性について正しく理解します。なぜ忘れっぽいのか、なぜ集中できないのか、そのメカニズムを知ることで、自分を責める気持ちが減り、冷静に対策を考えられるようになります。
認知行動療法 (CBT)
自分の思考パターンや行動の癖に気づき、より適応しやすい考え方や行動を身につけていくためのトレーニングです。例えば、「どうせまた失敗する」という考えを「どうすれば失敗しにくくなるか工夫してみよう」と切り替えたり、タスクを小さなステップに分解して管理する方法を学んだりします。
環境調整
集中を妨げる刺激を減らす(例:仕事机の周りを整理する、パーテーションを使う)、忘れてはいけないことを可視化する(例:スマートフォンのリマインダーやアプリ、目立つ場所のホワイトボードを活用する)など、物理的な環境を工夫することで、困難をカバーします。また、職場の同僚や上司、家族に特性について説明し、理解と協力を得ることも非常に重要です。
薬物療法
心理社会的治療や環境調整だけでは困難が続く場合、薬物療法も効果が期待できます。ADHD治療薬は、脳内の神経伝達物質(ノルアドレナリンやドーパミン)のバランスを整えることで、不注意や多動性・衝動性といった中核症状を改善する効果があります。
現在、日本で成人のADHDに対して使用が認められている主な薬には、アトモキセチン(ストラテラ)、メチルフェニデート(コンサータ)、グアンファシン(インチュニブ)などがあります。これらの薬を服用することで、「集中力が高まった」「衝動的に行動することが減った」「頭の中の騒がしさが静かになった」といった効果が期待できます。
もちろん、どのような薬にも副作用の可能性はありますので、医師が効果と副作用のバランスを慎重に見ながら、ご本人に合った薬と量を調整していきます。
ADHD(注意欠如・多動症)
のまとめ
ADHDについて解説してきましたが、最もお伝えしたいのは、ADHDは「欠点」ではなく、あくまで「特性」の一つであるという視点です。確かに、その特性によって困難を感じる場面は多いかもしれません。しかし、適切な治療や工夫によって、その困難は軽減できます。
治療に取り組むことは、単に症状を抑えるだけでなく、ご自身をより理解することになります。自分の得意なこと、苦手なことを理解し、苦手な部分はツールや周りの助けを借りて補い、得意な部分を活かしていく。そうすることで、「自分は社会に適応できないのではないか」という不安は、少しずつ「自分らしく社会と関わっていくにはどうすればいいか」という前向きな問いに変わっていくはずです。
この記事を読み、「一度専門家に相談してみようか」という気持ちが少しでも生まれたなら、それは大変素晴らしいことです。クリニックの扉を開けることは、少し勇気がいるかもしれません。しかし、その一歩が、あなたの未来をより生きやすくする転機となるかもしれないのです。当院ではそれぞれに合った最善の治療法を一緒に考え、安心して治療に取り組めるようサポートします。