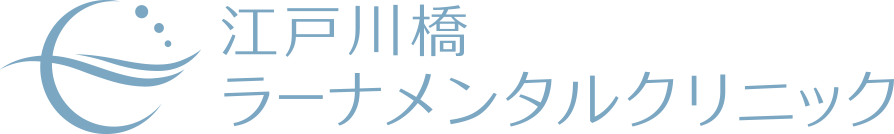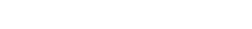眠れない・眠りが浅い・
日中も眠い
 「最近よく眠れない」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」-このような睡眠の悩みを抱えていませんか?
「最近よく眠れない」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」-このような睡眠の悩みを抱えていませんか?
睡眠は私たちの心身の健康を保つために欠かせない生理現象です。しかし、現代社会では約5人に1人が何らかの睡眠の問題を抱えているといわれています。睡眠障害は単に「眠れない」だけでなく、日中の活動や生活の質に大きな影響を与え、放置すると様々な心身の不調につながる可能性があります。
睡眠の問題は、ストレスや生活習慣の乱れだけでなく、背景に別の疾患が隠れていることもあります。この記事では、睡眠の悩みについて、その背景にある症状や原因、そして考えられる病気について解説します。
他にこのような症状は
ありませんか?
睡眠障害と一緒に現れやすい症状をチェックしてみましょう。これらの症状の有無は、原因となる疾患を見極める重要な手がかりになります。
精神面の症状
- 気分の落ち込み、憂うつ感
- 不安感、緊張感、イライラ
- 意欲や興味の低下
- 集中力・記憶力の低下
- 死にたい気持ち(希死念慮)
身体面の症状
- 頭痛、頭重感
- 動悸、息苦しさ
- 食欲の変化(食欲不振または過食)
- 体重の変化
- 疲労感、だるさ
- 便秘、下痢などの消化器症状
睡眠に関連する特徴的な症状
- いびき、睡眠中の呼吸停止
- 脚のムズムズ感、不快感
- 睡眠中の異常行動(寝言、歯ぎしり、手足の動き)
- 悪夢、金縛り
- 日中の強い眠気、居眠り
「眠れない」を
引き起こす原因
睡眠の問題は、一つの原因だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合って生じることが少なくありません。
- 心理的な原因:仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、将来への不安などのストレスは、交感神経を興奮させ、心身を緊張状態にして寝つきを悪くします。また、うつ病や不安症といった心の病気が背景にあることも多いです。
- 身体的な原因:睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群のように、睡眠そのものを妨げる病気が原因の場合があります。その他、アトピー性皮膚炎によるかゆみ、関節リウマチによる痛み、夜間頻尿なども睡眠を妨げる原因となります。
- 環境的な原因:寝室の騒音や明るさ、暑すぎ・寒すぎといった不適切な睡眠環境は、眠りの質を大きく低下させます。枕やマットレスが体に合っていないことも原因の一つです。
- 生活習慣の原因:夜勤などによる不規則な生活リズム、就寝前のスマートフォンやPCの利用(ブルーライトの影響)、カフェインの過剰摂取、アルコール(眠りを浅くします)やニコチンの摂取などが挙げられます。
主な疾患(鑑別)
睡眠障害の症状や原因によって、考えられる疾患は異なります。ここでは代表的な疾患と、それぞれの睡眠障害の特徴、簡単な治療法について説明します。また、身体的な原因、環境的な原因、生活習慣の原因がある場合は、それらの改善も行います。
不眠症
症状の特徴
寝つきが悪い(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、ぐっすり眠った感じがしない(熟眠障害)といった症状が続き、日中の倦怠感、意欲低下、集中力低下などの不調が現れる状態です。原因はストレス、生活習慣の乱れ、精神疾患、身体疾患など様々です。
治療法
睡眠衛生指導(生活習慣の改善)に加えて、薬物療法を検討します。また、原因となっている精神疾患や身体疾患があれば、その治療も並行して行います。認知行動療法(CBT-I)も有効な治療法の一つです。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
症状の特徴
睡眠中に呼吸が一時的に止まったり、浅くなったりすることを繰り返す疾患です。大きないびきや日中の強い眠気、起床時の頭痛などが特徴です。肥満や顎の形状などが関与していることが多いです。睡眠中に何度も呼吸が止まるため、脳が覚醒しやすく、眠りが浅くなります。本人は無呼吸に気づいていないことも多いですが、熟眠感が得られず、日中に強い眠気を感じます。
治療法
CPAP(シーパップ)療法という、鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ治療法が一般的です。その他、マウスピースの装着や、原因と重症度によっては外科手術を行うこともあります。生活習慣の改善(減量、禁煙、節酒など)も重要です。
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
症状の特徴
 主に夕方から夜間にかけて、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる疾患です。じっとしていると症状が悪化し、動かすと一時的に楽になります。脚の不快感のために入眠困難になったり、睡眠中に目が覚めてしまったりします。
主に夕方から夜間にかけて、脚(時には腕などにも)に「むずむずする」「虫が這うような」「ピリピリする」といった不快な感覚が現れ、脚を動かさずにはいられなくなる疾患です。じっとしていると症状が悪化し、動かすと一時的に楽になります。脚の不快感のために入眠困難になったり、睡眠中に目が覚めてしまったりします。
治療法
鉄分不足が原因の一つと考えられており、鉄剤の補充を行うことがあります。その他、ドパミン作動薬や非ドパミン作動薬などの薬物療法が有効です。生活習慣の改善(カフェインやアルコールの制限、適度な運動など)も推奨されます。
概日リズム睡眠・覚醒障害
症状の特徴
体内時計のリズムが乱れ、望ましい時刻に睡眠・覚醒することが困難になる状態です。以下のようなタイプがあります。
- 睡眠相後退型: 深夜にならないと眠れず、朝起きられない。
- 睡眠相前進型: 夕方早くに眠くなり、早朝に目が覚めてしまう。
- 非24時間睡眠・覚醒リズム型: 睡眠と覚醒の時間が毎日少しずつ遅れていく。
- 不規則睡眠・覚醒リズム型: 睡眠と覚醒のパターンが不規則で、まとまった睡眠がとれない。
治療法
高照度光療法(朝に強い光を浴びる)、メラトニン受容体作動薬、時間療法(就寝時刻を少しずつずらしていく)などが行われます。規則正しい生活習慣を確立することも重要です。
うつ病・適応反応症(適応障害)・双極症(双極性障害)
症状の特徴
気分の落ち込みや意欲の低下などを主症状とするうつ病や適応反応症、うつ状態と躁状態を繰り返す双極症では、睡眠障害が高頻度に見られます。
睡眠障害の特徴
- うつ病・適応反応症: 入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害など、様々なタイプの不眠が現れます。逆に、過眠(寝過ぎてしまう)が見られることもあります。
- 双極症: 躁状態の時は睡眠時間が極端に短くても平気になったり(睡眠欲求の減少)、うつ状態の時は不眠・過眠になることがあります。
治療法
抗うつ薬や気分安定薬などによる薬物療法と精神療法が中心となります。睡眠障害に対しては、睡眠薬を併用することもありますが、まずは原因となっているうつ病や双極性障害の治療が優先されます。
不安症(不安障害)
症状の特徴
全般性不安症、パニック症、社交不安症など、過度な不安や恐怖を主症状とする疾患群です。不安や緊張感から寝つきが悪くなったり(入眠困難)、夜中に目が覚めて不安なことを考えてしまったり(中途覚醒)することが多く見られます。悪夢を見ることもあります。
治療法
抗うつ薬(SSRI・SNRIなど)や抗不安薬による薬物療法、認知行動療法などの精神療法が行われます。リラクゼーション法(呼吸法、自律訓練法など)も不安の軽減と入眠の助けになります。
よくある質問(Q&A)
一般的に、週3回以上の睡眠困難が3か月以上続く場合、慢性不眠症と診断されます。
例えば、睡眠時無呼吸症候群では呼吸停止によって睡眠が中断されますし、レストレスレッグス症候群では脚の不快感で入眠が妨げられます。また、概日リズム睡眠障害では、体内時計のずれによって望ましい時間に眠れなくなります。これらは不眠症とは異なる疾患として扱われ、治療法も異なります。
睡眠ポリグラフ検査(PSG)は、通常の不眠症では必須ではありません。ただし、睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群、ナルコレプシーなど、他の睡眠障害が疑われる場合には重要な検査となります。また、レストレスレッグス症候群が疑われる場合は、鉄欠乏を調べるための血液検査(フェリチン、鉄パネル)が推奨されます。
不眠症との重要な違いは、睡眠時無呼吸症候群では中途覚醒の自覚がないことが多く、むしろ「日中の強い眠気」が主な症状となる点です。また、いびきや肥満、高血圧などを伴うことが多いのも特徴です。ただし、両者が併存することもあります。
その他のリスク因子には、男性であること、高齢、首周りが太いこと(男性で43cm以上、女性で38cm以上)、いびきの習慣があります。ただし、肥満でなくても睡眠時無呼吸症候群を発症することはあります。実際、睡眠時無呼吸症候群患者の約44%は過体重、約23%は正常体重または低体重です。
重要なのは、いびき、日中の強い眠気、肥満、高血圧などの睡眠時無呼吸症候群の特徴がないかを確認することです。睡眠時無呼吸症候群を見逃すと、CPAP療法など効果的な治療を受ける機会を失うことになります。不眠症の治療で改善しない場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性を考える必要があります。
患者さんは「這うような感覚」「ピリピリする」「引っ張られる」「痛む」「電気が走る」などと表現されます。この症状は夕方から夜間に悪化し、脚を動かすと一時的に楽になるという特徴があります。不眠症との違いは、明確な身体症状(不快感)があり、それが入眠を妨げている点です。
レストレスレッグス症候群の診断には、①脚を動かしたい衝動と不快感、②安静時に悪化、③動くと軽減、④夜間に悪化、という4つの基準があります。また、レストレスレッグス症候群と睡眠時無呼吸症候群が併存することもあり、21%程度の患者さんで両者が見られるという報告があります。
その他の重要なリスク因子には、妊娠(特に妊娠後期)、末期腎不全、パーキンソン病があります。また、約60%の患者さんに家族歴があり、遺伝的要因も関与しています。一部の抗うつ薬、抗精神病薬、抗ヒスタミン薬などの薬剤も症状を悪化させることがあります。
また、末期腎不全の患者さんでは、レストレスレッグス症候群の有病率が非常に高く、透析患者の19.4〜57.3%がレストレスレッグス症候群を経験しています。腎不全患者でレストレスレッグス症候群が多い理由は、鉄欠乏、貧血、電解質異常、末梢神経障害などが関与していると考えられています。
不眠症との違いは、「望ましい時間に眠れない」けれど「体内時計に合った時間なら十分に眠れる」という点です。例えば、睡眠相後退症候群の人は深夜3時までは眠れませんが、3時以降なら問題なく眠れます。不眠症では、どの時間帯でも入眠や睡眠維持に困難があります。
ナルコレプシーと不眠症の大きな違いは、ナルコレプシーでは入眠後すぐにレム睡眠に入ること、日中に突然眠り込む「睡眠発作」があること、そして情動脱力発作(カタプレキシー)が見られることです。睡眠検査で明確に区別できます。ナルコレプシーは比較的まれな疾患で、米国の一般集団では10万人あたり約38人(約0.04%)の有病率です。
重要な違いは、特発性過眠症では総睡眠時間が11時間以上と長いこと、昼寝をしても「すっきりしない」こと、起床時に強い睡眠慣性(目覚めの悪さ)があることです。また、睡眠検査では8分以内に入眠するという客観的な所見があります。
不眠症との違いは、睡眠不足症候群では「眠る時間さえあれば眠れる」という点です。週末や休暇中に長時間眠ることができ、症状が改善します。不眠症では、時間があっても眠れません。ただし、睡眠不足症候群は医学的な診断名として一般的に使われる病名ではなく、むしろ生活習慣の問題として扱われることが多い概念です。
これらは不眠症とは異なり、「睡眠中の異常な出来事」が主な症状です。例えば、レム睡眠行動障害では、夢の内容を行動化してしまい、叫んだり暴れたりします。夜驚症では、睡眠中に突然起き上がって恐怖を表現しますが、本人は翌朝覚えていません。これらは睡眠の質の問題であり、入眠困難とは本質的に異なります。
うつ病では、不眠以外に気分の落ち込み、興味や喜びの喪失、食欲低下、集中力低下などの症状が2週間以上続きます。また、時系列も重要で、うつ病の症状と同時期に不眠が始まった場合は、うつ病に伴う不眠と考えられます。逆に、長期間の不眠症は、うつ病の発症リスクを1.5〜3.9倍に高めることも知られています。
鑑別のポイントは、日中の不安症状の有無です。不安障害では、過度の心配、緊張、身体症状(動悸、発汗など)が日中も持続します。また、PTSDでは悪夢による覚醒が特徴的であり、これは単純な不眠症とは区別されます。
これらの疾患による不眠は「二次性不眠」と呼ばれ、原疾患の治療が最優先となります。例えば、胃食道逆流症では就寝中の胃酸逆流によって覚醒が生じますし、心不全では起坐呼吸(横になると息苦しい)のために睡眠が妨げられます。詳しい問診と身体診察が鑑別に重要です。
さらに、睡眠薬やアルコールの長期使用後に突然中止すると、反跳性不眠(リバウンド不眠)が生じることがあります。このような物質誘発性睡眠障害は、不眠症とは区別して診断され、原因物質の中止や変更が治療の基本となります。
ただし、これらは正常な加齢変化であり、必ずしも病的な不眠症ではありません。高齢者で不眠を訴える場合は、睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群、周期性四肢運動障害、認知症に伴う睡眠障害などの可能性を考慮する必要があります。また、服用している薬剤の影響も重要です。
これは不眠症の原因にもなりますが、診断上は区別されます。不適切な睡眠衛生が主な原因であれば、生活習慣の改善だけで症状が改善することが多いのです。逆に、睡眠衛生を改善しても不眠が続く場合は、不眠症やその他の睡眠障害を考える必要があります。
精神疾患や身体疾患を抱えている人も不眠症のリスクが高くなります。不眠症患者の約40%が何らかの精神疾患を併発しており、特にうつ病や不安障害との関連が強いことが分かっています。また、夜勤や交代勤務をしている人も不眠症のリスクが高まります。
閉経期の女性では、ホットフラッシュなどの血管運動症状が慢性不眠症の重要な誘発因子となります。また、妊娠中や産後も睡眠の質が低下しやすい時期です。ホルモン変動が睡眠に影響を与えていると考えられています。
ただし、閉経後の女性では睡眠時無呼吸症候群のリスクが上昇し、男性に近づきます。これは、閉経前の女性ではエストロゲンやプロゲステロンが気道を保護している可能性があるためと考えられています。また、肥満が睡眠時無呼吸症候群に与える影響も男女で異なるメカニズムが関与していることが示されています。
非肥満の睡眠時無呼吸症候群患者では、頭蓋骨の構造的異常(小顎症、後退顎など)、軟口蓋の組織異常、巨舌症などの解剖学的要因が原因となることが多いです。また、遺伝的要因、喫煙、飲酒、胃食道逆流症なども関与します。非肥満患者では、軽度の睡眠時無呼吸症候群(AHI<15)が多い傾向があります。
さらに、糖尿病、高血圧、肥満などのリスクも上昇します。QOL(生活の質)の低下も顕著で、仕事や学業のパフォーマンス低下、対人関係への影響も見られます。早期の適切な治療が重要です。
毎年、米国人の約25%が急性不眠を経験しますが、その約75%は慢性不眠症に進行せずに改善します。ただし、一度慢性化すると長期にわたって症状が続くことが多く、適切な治療介入が重要です。
週3回以上の睡眠困難が続いている、日中の疲労や集中力低下で生活に支障が出ている、いびきや呼吸停止を指摘された、脚の不快感で眠れない、日中に強い眠気があり居眠りしてしまう――こういった状況です。また、うつ症状や不安症状を伴う場合、市販の睡眠薬に頼っている場合も、専門的な評価と治療が必要です。不眠症だけでなく、他の睡眠障害や精神疾患が隠れている可能性もあるため、適切な診断を受けることが大切です。慢性化する前の早期受診が、より良い治療結果につながります。
まとめ
 睡眠の悩みは、単に「眠れない」という問題だけでなく、その背景に心や体の様々なサインが隠されています。もし、あなたの睡眠の問題が長く続いている、あるいは日中の活動に支障が出ていると感じるなら、それは専門家への相談を考えるタイミングかもしれません。
睡眠の悩みは、単に「眠れない」という問題だけでなく、その背景に心や体の様々なサインが隠されています。もし、あなたの睡眠の問題が長く続いている、あるいは日中の活動に支障が出ていると感じるなら、それは専門家への相談を考えるタイミングかもしれません。