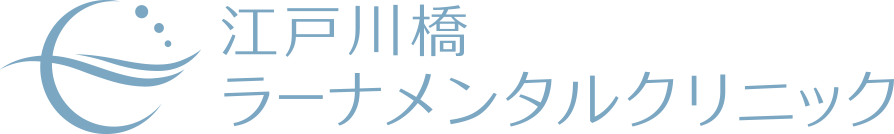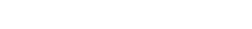- この記事のポイント
- 不眠症とは
- 不眠症の主な症状と特徴
- 不眠症の原因として考えられていること
- 不眠症はどのくらいの人が経験するのか
- 不眠症の診断はどのように行われるのか
- 不眠症の治療法と回復への道のり
- 他の睡眠障害
- よくある質問(Q&A)
- 不眠症・睡眠障害のまとめ
この記事のポイント
- 不眠症は、適切な睡眠の機会があるにもかかわらず、眠ることが困難な状態が続く疾患です。
- 不眠の背景には様々な要因があり、それぞれに応じた対処法があります。
- 不眠症以外にも睡眠に関する病気があり、それぞれ治療を必要とします。
不眠症とは
 不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、日中の生活にも影響を与える重要な健康問題です。WHO(世界保健機関)によれば、不眠症は「睡眠の開始や維持の困難、または回復感のない睡眠を特徴とする状態」と定義されています。
不眠症は、単に「眠れない」というだけでなく、日中の生活にも影響を与える重要な健康問題です。WHO(世界保健機関)によれば、不眠症は「睡眠の開始や維持の困難、または回復感のない睡眠を特徴とする状態」と定義されています。
この記事では、不眠症について医学的に正確な情報を、分かりやすく解説していきます。
不眠症の主な症状と特徴
不眠症の症状は、夜間の睡眠困難だけでなく、日中の生活全般に影響を及ぼします。
夜間の睡眠に関する症状
不眠症の中核となる症状として、以下のようなものがあります。入眠困難(寝つきが悪い)は、布団に入ってから30分以上経っても眠りにつけない状態を指します。中途覚醒は、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか眠れない状態です。早朝覚醒は、予定より2時間以上早く目が覚めてしまい、再び眠ることができない状態を指します。
これらの症状は単独で現れることもあれば、複数が組み合わさることもあります。
日中の心身への影響
不眠症は夜間だけの問題ではありません。日中には、疲労感や倦怠感、集中力の低下、イライラ感、気分の落ち込みなどが現れます。仕事や家事の効率が落ちたり、人間関係にも影響が出ることがあります。また、頭痛や胃腸の不調、食欲の変化なども起こりやすくなります。
生活の質への影響
これらのこころとからだの不調は、私たちの日常生活や社会生活にも様々な影響を及ぼします。
仕事や学業のパフォーマンス低下
集中力や判断力の低下により、仕事上のミスが増えたり、学業成績が下がったりすることがあります。重要な会議中に眠気を感じたり、効率が著しく落ちたりすることもあります。
人間関係の悪化
イライラしやすくなったり、気分の浮き沈みが激しくなったりすることで、家族や友人、同僚との関係がぎくしゃくしてしまうことがあります。
事故のリスク増加
日中の強い眠気により、居眠り運転や作業中の事故のリスクが高まります。
生活の質の低下
趣味を楽しめなくなったり、外出が億劫になったりするなど、全般的な生活の質(QOL:Quality of Life)が低下してしまうことがあります。
不眠症の原因として
考えられていること
不眠症の原因は人それぞれ異なり、多くの場合、複数の要因が絡み合って発症します。
生物学的要因
体内時計(概日リズム)の乱れは、不眠症の重要な要因の一つです。交代勤務や時差ボケ、不規則な生活リズムなどが体内時計を狂わせます。また、脳内の神経伝達物質のバランスの変化も睡眠に影響を与えます。年齢とともに睡眠パターンが変化することも自然な現象ですが、それが不眠症につながることもあります。
心理的要因とストレス
仕事や人間関係のストレス、将来への不安、過去の出来事へのとらわれなど、心理的な要因は不眠症の大きな原因となります。「今夜も眠れないのではないか」という不安自体が、さらに眠りを妨げるという悪循環に陥ることもあります。
環境的・生活習慣的要因
寝室の環境(温度、湿度、明るさ、騒音)、カフェインやアルコールの摂取、スマートフォンなどの画面を寝る前に見ること、運動不足なども不眠の原因となります。これらは比較的改善しやすい要因でもあります。
不眠症はどのくらいの人が
経験するのか
不眠症は決して珍しい疾患ではありません。むしろ、多くの方が人生のどこかで経験する一般的な健康問題です。
日本の成人の約20%が慢性的な不眠を訴えており、約5%が不眠症の診断基準を満たすという調査結果があります。つまり、20人に1人は不眠症で悩んでいることになります。さらに、一時的な不眠を含めると、成人の約30%が何らかの睡眠の問題を抱えているとされています。
年齢と性別による違い
不眠症は年齢とともに増加する傾向があり、特に60歳以上では約3人に1人が不眠の症状を訴えているという調査結果もあります。これは加齢に伴う睡眠パターンの変化が影響していると考えられています。性別では、女性の方が男性よりも不眠症になりやすく、特に更年期前後で増加する傾向があります。これはホルモンバランスの変化が関係していると考えられています。
発症しやすい時期
大きなライフイベント(就職、結婚、出産、転職、退職など)の前後、季節の変わり目、ストレスが多い時期などに不眠症は発症しやすくなります。また、他の精神疾患(うつ病、不安障害など)や身体疾患(痛み、呼吸器疾患など)に伴って現れることもあります。
不眠症の診断は
どのように行われるのか
不眠症の診断は、専門医による丁寧な問診と評価により行われます。自己判断ではなく、専門家の診断を受けることが、適切な治療への第一歩となります。
診断基準について
精神疾患の国際的な診断基準として、主に「DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)」や「ICD-11(国際疾病分類 第11版)」が用いられます。不眠症の診断も、これらの基準に基づいて行われます。
例えば、DSM-5-TRにおける不眠障害の診断基準の主なポイントは以下の通りです(簡略化して記載しています)。
- A. 睡眠の量または質に関する不満で、以下のうち1つ(またはそれ以上)の症状がある:
- 入眠困難
- 睡眠維持の困難(例:しばしば目が覚める、または再入眠困難)
- 早朝覚醒し、再入眠困難
- B. その睡眠困難が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、教育的、学業的、行動的、または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
- C. その睡眠困難が、少なくとも週に3回起こる。
- D. その睡眠困難が、少なくとも3ヶ月間持続する。
- E. その睡眠困難が、睡眠のための適切な機会があるにもかかわらず起こる。
- F. その不眠が、他の睡眠覚醒障害(例:睡眠時無呼吸症候群、概日リズム睡眠覚醒障害)ではうまく説明されず、それらの経過中にのみ起こるものではない。
- G. その不眠が、物質(例:乱用薬物、医薬品)の生理学的作用によるものではない。
- H. 併存する精神疾患や身体疾患では、その不眠の訴えが適切に説明されない。
これらの基準は専門家が用いるものであり、ご自身でチェックリストのように使うためのものではありません。あくまで参考としてご理解ください。
診断のプロセス
まず問診で、睡眠の状況に加えて、生活習慣、ストレス要因、既往歴、服用中の薬などについても確認します。睡眠日誌(就寝時刻、起床時刻、夜間の覚醒回数などを記録)をつけていただくこともあります。
必要に応じて、睡眠ポリグラフ検査(睡眠中の脳波、心電図、呼吸などを測定)や、アクチグラフ(腕時計型の活動量計)による評価を行うこともあります。また、他の睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群など)や身体疾患、精神疾患との鑑別も重要です。
不眠症の治療法と
回復への道のり
不眠症の治療には様々な選択肢があり、それぞれの方の状況に応じて最適な方法を選択します。治療の目標は、単に眠れるようになることだけでなく、日中の生活の質を改善し、健康的な睡眠習慣を身につけることです。
薬物療法
 ベンゾジアゼピン系睡眠薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など、作用機序の異なる様々な薬があります。最近では、効果と安全性の面から、オレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬が主に用いられます。
ベンゾジアゼピン系睡眠薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、メラトニン受容体作動薬、オレキシン受容体拮抗薬など、作用機序の異なる様々な薬があります。最近では、効果と安全性の面から、オレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬が主に用いられます。
不眠のタイプ(入眠困難型、中途覚醒型、早朝覚醒型)や、日中の活動への影響、他の疾患の有無などを考慮して、最適な薬を選択します。「一生やめられなくなるのでは」という心配をされる方もいますが、オレキシン受容体拮抗薬、メラトニン受容体作動薬に関しては依存性はとても低いので、多くの場合、症状が改善すれば徐々に減量・中止することができます。
認知行動療法(CBT-I)
不眠症に対する認知行動療法(CBT-I)は、薬を使わない治療法として高い効果が認められています。睡眠に対する誤った認識や不安を修正し、良い睡眠習慣を身につけるための方法です。
刺激統制法(寝室を睡眠だけの場所にする)、睡眠制限法(実際に眠れる時間に合わせて寝床にいる時間を調整)、リラクセーション法(筋弛緩法、呼吸法など)などの技法を組み合わせて行います。
生活習慣の改善と睡眠衛生
睡眠衛生とは、良質な睡眠を得るための生活習慣のことです。規則正しい睡眠スケジュールを保つ、寝室を快適な環境に整える、カフェインやアルコールを控える、適度な運動を取り入れる、寝る前のスマートフォン使用を避けるなど、日常生活の中でできることがたくさんあります。
これらの改善は、薬物療法や認知行動療法と併用することで、より効果的になります。完璧を求めすぎず、できることから少しずつ始めることが大切です。
他の睡眠障害
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が停止または低下する疾患です。大きないびきとともに、日中の強い眠気が特徴的で、放置すると高血圧や心血管疾患のリスクが高まります。
治療の第一選択はCPAP(持続陽圧呼吸療法)で、マスクを通じて気道に空気を送り込みます。軽症例では体重減少や側臥位での睡眠、口腔内装置(マウスピース)の使用も有効です。重症例では扁桃摘出術などの外科的治療を検討することもあります。
ナルコレプシー
ナルコレプシーは日中の過度の眠気と突然の睡眠発作を特徴とする神経疾患です。感情が高ぶった時に全身の力が抜ける情動脱力発作(カタプレキシー)、金縛りのような睡眠麻痺、入眠時の幻覚などの症状も伴います。これらはレム睡眠の調節異常によって生じます。
治療にはモダフィニルやメチルフェニデートなどの覚醒促進薬を使用し、カタプレキシーには抗うつ薬が有効です。また、計画的な短時間の昼寝を取り入れることで症状の改善が期待できます。
レストレスレッグス症候群
レストレスレッグス症候群は、夕方から夜間にかけて脚に不快感が生じ、脚を動かしたいという強い衝動に駆られる疾患です。この症状は安静時に悪化し、脚を動かすことで一時的に改善するという特徴があり、入眠困難の原因となります。
治療にはドパミン作動薬のプラミペキソールやロピニロールが第一選択となり、鉄欠乏がある場合は鉄分補充も行います。ガバペンチンやプレガバリンも有効で、カフェインやアルコールの制限などの生活習慣の改善も重要です。
概日リズム睡眠覚醒障害
概日リズム睡眠覚醒障害は、体内時計と社会的な生活リズムのずれによって生じます。睡眠相後退症候群では極端な夜型となり、睡眠相前進症候群では極端な朝型となります。非24時間睡眠覚醒症候群では睡眠時間が毎日少しずつ後ろにずれていき、交代勤務睡眠障害では不規則な勤務により睡眠リズムが乱れます。
治療には朝の光曝露による光療法、メラトニン投与、段階的に睡眠時間を調整する時間療法などを用い、可能な範囲で社会的スケジュールの調整も行います。
レム睡眠行動障害
レム睡眠行動障害は、通常レム睡眠中に生じる筋弛緩が失われることで、夢の内容に応じて叫んだり暴れたりする行動が現れる疾患です。これにより本人や同床者が怪我をするリスクがあり、パーキンソン病などの神経変性疾患の前駆症状である可能性も指摘されています。
治療にはクロナゼパムやメラトニンが有効で、睡眠環境の安全確保も重要です。また、基礎疾患の評価と適切な治療も必要となります。
よくある質問(Q&A)
睡眠や不眠症について、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
不眠症・睡眠障害のまとめ
ここまで不眠症・睡眠障害について見てきました。「精神科や心療内科を受診することに抵抗がある」「睡眠薬に頼りたくない」「こんなことで相談していいのだろうか」…そういったためらいや不安を感じるお気持ちは、とてもよく分かります。特に、メンタルヘルスの問題は、周囲に相談しにくかったり、一人で抱え込んでしまったりしがちです。一方で、「また今夜も眠れないのではないか」「仕事のパフォーマンスが落ちて、職を失うかもしれない」、という不安によりまた眠れなくなるという悪循環もあるかと思います。このような状況を改善したいと思ったら、まずは相談だけでも構いません、受診してみてください。