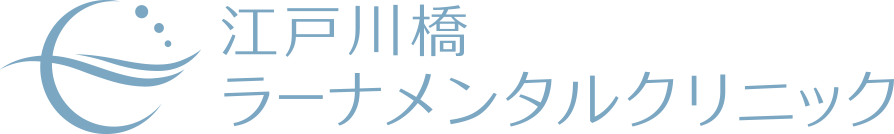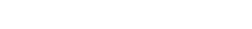はじめに
 「理由もなく急に不安になる」「動悸がして息苦しい」「何か悪いことが起きそうで怖い」――このような症状でお悩みではありませんか?
「理由もなく急に不安になる」「動悸がして息苦しい」「何か悪いことが起きそうで怖い」――このような症状でお悩みではありませんか?
不安は誰もが経験する自然な感情ですが、日常生活に支障をきたすほど強い不安や、頻繁に起こる動悸は、適切な治療が必要な状態かもしれません。不安症状の背景には様々な原因があり、それぞれに応じた治療法があります。
不安や動悸に伴いやすい症状
不安や動悸という症状に加えて、以下のようなお悩みはありませんか?これらの症状は、原因を探していく上で重要な手がかりとなることがあります。心当たりがある場合は、問診や診察時にお伝えください。
身体の症状
- めまい、ふらつき
- 息苦しさ、過呼吸
- 胸の圧迫感、胸の痛み
- 吐き気、腹部の不快感
- 発汗、手足の震え
- 頭痛、肩こり
- 不眠(寝付けない、途中で目が覚める、熟睡感がない)
- 食欲不振または過食
- 疲れやすい、倦怠感
こころの症状
- 過度な心配事(仕事、健康、家族のことなど)が頭から離れな
- 集中できない、落ち着かない
- イライラしやすい、怒りっぽい
- 何も楽しめない、興味がわかない
- 突然、強い恐怖感に襲われる(パニック発作)
- 特定の場所や状況を避けるようになる(例:電車、人混み、発表の場など)
- 自分が自分でないような感覚、現実感がない
- 何か恐ろしいことが起きるのではないかという予期不安
行動面の変化
- 回避行動(特定の場所や状況を避ける)
- 外出困難
- 確認行為の増加
- アルコールや薬物への依存
不安や動悸を来す主な疾患
不安や動悸といった症状は、様々なこころの病気や身体の病気の一つのサインとして現れることがあります。症状や検査結果などから、以下のような疾患が考えられます。
全般性不安症(全般性不安障害)
全般性不安症は、特定のことだけでなく、日常生活の様々なことに対して過剰でコントロール困難な心配や不安が長期間(通常6ヶ月以上)続く病気です。それに伴い、落ち着きのなさ、疲れやすさ、集中困難、筋肉の緊張、不眠などの身体症状が現れます。
全般性不安症の不安や動悸は、特定の対象がない漠然としたものであり、持続的である点が特徴です。常に緊張状態にあるため、動悸を感じやすい傾向があります。
治療法は、薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬、抗不安薬)と精神療法(認知行動療法、リラクセーション法など)が中心となります。不安をコントロールする方法を学び、日常生活の支障を軽減することを目指します。
パニック症(パニック障害)
パニック症は、突然、理由もなく激しい不安感や恐怖感に襲われ、パニック発作が繰り返し起こる病気です。パニック発作がまた起こったらどうしようという、予期不安を伴います。
パニック症の不安や動悸は、状況によらず起こるパニック発作が特徴です。
治療は薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬、抗不安薬)と精神療法(認知行動療法など)を組み合わせて行います。薬物療法で発作をコントロールしつつ、認知行動療法で発作への対処法や誤った認知の修正を行います。
広場恐怖症
公共交通機関や映画館、美容室、列に並ぶ、といった状況のうち2つ以上に対して著しい恐怖や不安を感じ、時にこれらの状況を積極的に避けようとします。(1つの場合は限局性恐怖症と言います)
広場恐怖症の不安や動悸は、特定の逃げ場がない、助けが来ることができない状況で起こってくるのが特徴です。
治療は薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬、抗不安薬)と精神療法(認知行動療法、段階的暴露療法など)を組み合わせて行います。
社交不安症/社交不安障害
社交不安症は、人前で話す、注目を浴びる、人と交流するなどの社交場面(例:人前で話す、電話をする、食事をする、会議で発言する)に対して、不安を感じ、時としてそのような状況を避けようとする病気です。そのような社交場面に直面すると、不安に加えて、動悸、赤面、発汗、震え、吐き気などの身体症状も現れます。
社交不安症における不安や動悸は、特定の社交場面で顕著に現れる点が特徴です。
治療は薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬、抗不安薬)と精神療法(認知行動療法、段階的暴露療法など)を組み合わせて行います。
強迫症(強迫性障害)
自分でも不合理だと分かっていながら、特定の考え(強迫観念)が繰り返し頭に浮かび、それを打ち消すための行為(強迫行為)を繰り返さずにはいられなくなります。例えば、「手が汚れているのではないか」という強迫観念から何度も手を洗い続けたり、「鍵を閉め忘れたのではないか」と何度も確認したりします。これらの行為に多くの時間を費やし、日常生活に支障をきたします。
強迫症の不安(強迫観念)は、自分でも不合理だと分かっていながら、それを打ち消すために強迫行為を繰り返さずにはいられない、ということが特徴となります。
治療は薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬、抗不安薬)と精神療法(認知行動療法、段階的暴露療法など)を組み合わせて行います。
うつ状態(うつ病/双極症/適応反応性など)
うつ状態では、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失といった症状に加えて、不安、焦燥感、集中力の低下、睡眠障害、食欲の変化などを伴い、時に不安症状が前面に出ることもあります。
うつ状態では、仮に不安が前面に出ていたとしても、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失など、多彩な症状が見られます。不安以外の症状を、問診で丁寧に確認していくことで、不安症や他の病気と区別していきます。
治療は、うつ病、双極症、適応反応症といった、うつ状態の原因となっている病気の治療法に準じます。
身体疾患に伴う不安
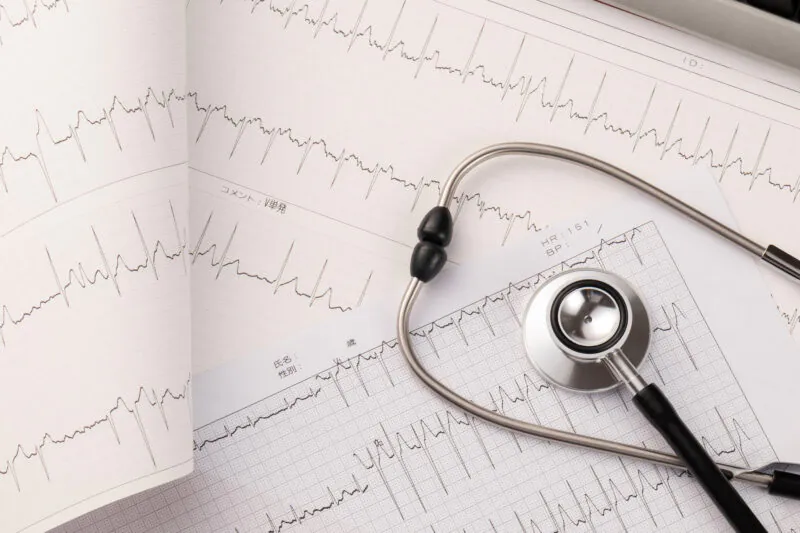 甲状腺機能亢進症、不整脈、貧血、低血糖、更年期障害、呼吸器疾患(喘息など)、心疾患などが原因で、動悸、息切れ、発汗、震えといった身体症状が現れ、これらに不安が伴うことがあります。
甲状腺機能亢進症、不整脈、貧血、低血糖、更年期障害、呼吸器疾患(喘息など)、心疾患などが原因で、動悸、息切れ、発汗、震えといった身体症状が現れ、これらに不安が伴うことがあります。
問診と身体診察で、これらの病気が疑われる症状、所見があれば、検査を行い診断し、治療へとつなげていきます。
よくある質問 (Q&A)
- 公共交通機関の利用(特にすぐには降りられない特急列車や新幹線、高速道路など)
- 広い場所(駐車場、広場など)
- 閉鎖された空間(エレベーター、地下室、映画館など)
- 行列や人混み
- 一人での外出
- 不安や動悸の症状が6ヶ月以上続いている
- 特定の場所や状況を避けるようになり日常生活に支障が出ている
- 外出や通勤が困難になってきている
- 症状のために仕事や学業に集中できない
- 自分でも「過剰だ」と感じるほどの不安がある
まとめ
 診察では、問診で、詳しい症状や生活状況、ストレス要因、既往歴、家族歴、今内服している薬剤などを伺っていきます。また、血液検査などを行い、その結果も踏まえて診断し、一人ひとりに合わせた治療法をご提案いたします。
診察では、問診で、詳しい症状や生活状況、ストレス要因、既往歴、家族歴、今内服している薬剤などを伺っていきます。また、血液検査などを行い、その結果も踏まえて診断し、一人ひとりに合わせた治療法をご提案いたします。
不安や動悸は誰もが経験しうる症状です。「こんなことで受診していいのか」と悩まれる方も多いですが、日常生活に支障をきたすようになったら、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
早期の相談・治療開始が回復への近道です。一人ひとりに合わせた治療法をご提案し、つらい症状を改善して穏やかな日常を取り戻すお手伝いをいたします。