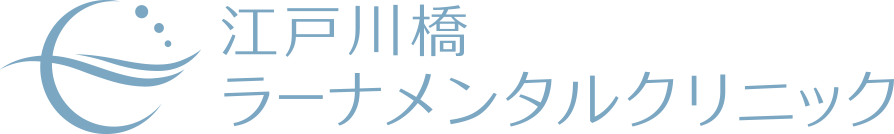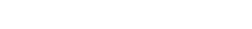疲れやすい・
心も体もしんどい
 「しっかり寝ているはずなのに、朝から体が重い」「理由もなく、やる気が出ない日が続く」 このような心と体の疲れ(倦怠感)は、多くの方が経験するありふれた症状です。しかし、それが長く続いたり、日常生活に支障をきたしたりするほどの「しんどさ」である場合、単なる疲れではなく、心や体が発しているサインかもしれません。
「しっかり寝ているはずなのに、朝から体が重い」「理由もなく、やる気が出ない日が続く」 このような心と体の疲れ(倦怠感)は、多くの方が経験するありふれた症状です。しかし、それが長く続いたり、日常生活に支障をきたしたりするほどの「しんどさ」である場合、単なる疲れではなく、心や体が発しているサインかもしれません。
他にこのような症状は
ありませんか?
疲れやすい・心も体もしんどいという症状と一緒に現れやすい症状をチェックしてみましょう。これらの症状の組み合わせは、原因を特定する重要な手がかりになります。
身体的な症状
- 睡眠の問題(不眠、過眠、途中覚醒、早朝覚醒)
- 食欲の変化(食欲低下、過食)
- 体重の変化(急激な増減)
- 頭痛、頭重感
- めまい、ふらつき
- 動悸、息切れ
- 消化器症状(胃痛、便秘、下痢)
- 筋肉痛、関節痛
- 微熱が続く
- 寒がり、暑がり
精神的な症状
- 気分の落ち込み、憂うつ
- 不安、焦燥感
- イライラしやすい
- 集中力・記憶力の低下
- 決断力の低下
- 興味・関心の減退
- 自己否定的な考え
- 希死念慮
主な疾患(鑑別)
「疲れやすい・心も体もしんどい」という症状が見られる代表的な疾患について、その特徴と治療法を解説します。ここでは精神的な病気から記載しますが、実際の診療では、原則として身体的な病気から考えて、その可能性が低そうなときに精神的な病気の可能性を考えていく、という順番になります。
うつ病(大うつ病性障害)
症状の特徴
うつ病の倦怠感は、「鉛のように体が重い」「泥の中に沈んでいるよう」と表現されるような、強い精神身体的な疲労感が特徴です。特に朝方に症状が最も重く、夕方にかけて少し楽になる(日内変動)傾向が見られます。何に対しても興味や喜びを感じられなくなる「興味・喜びの喪失」を伴うことが、診断上の重要なポイントです。
治療法
十分な休養を確保することが基本です。その上で、SSRIやSNRIといった抗うつ薬を中心とした薬物療法と、ものの受け止め方や考え方の癖を修正していく認知行動療法などの精神療法を組み合わせて治療を進めます。
適応反応症(適応障害)
症状の特徴
適応反応症では明確なストレス要因(例:職場環境の変化、人間関係のトラブル、転居など)があり、そのストレスに対する反応として心身に不調をきたす症状が生じます。原因となるストレスに直面している時に症状が強く現れ、ストレス源から離れると症状が和らぐ傾向があります。倦怠感も、ストレスの強さと密接に関連して変動するのが特徴です。
治療法
最も重要なのは、ストレスの原因となっている環境の調整です。可能であれば、ストレス源から一時的に離れる(休職など)ことも有効です。カウンセリングを通して、ストレスへの対処能力(コーピングスキル)を高めていくことも、回復と再発予防につながります。
双極症(双極性障害, 躁うつ病)
症状の特徴
双極症は、気分が著しく高揚する「躁状態」と、意欲が低下し気分が落ち込む「うつ状態」という両極端な状態を繰り返す病気です。かつては「躁うつ病」とも呼ばれていました。躁状態では、過度な自信、多弁、睡眠時間の短縮、浪費などの行動が見られることがあります。うつ状態では、倦怠感が見られることがあります。
治療法
気分の波を安定させることが治療の核となるため、気分安定薬や非定型抗精神病薬を用いた薬物療法が中心となります。心理教育を通して、自身の病気について理解を深め、再発のサインに早く気づけるようにすることも重要です。
不安症(全般性不安症(全般性不安障害)、パニック症(パニック障害)、社交不安症(社交不安障害)、広場恐怖症など)
症状の特徴
漠然とした過剰な心配や不安が長期間(通常6ヶ月以上)続く全般性不安症、状況によらず予期しないタイミングでパニック発作を繰り返し、予期不安を伴うパニック症、人前で注目を浴びる状況や、他人から否定的な評価を受ける可能性のある社交場面に対して、著しい恐怖や不安を感じる社交不安症、特定の逃げ出せない・助けが来られない状況に不安を感じる広場恐怖症、といった不安症でも、リラックスできず、疲労が蓄積していくことがあります。動悸、息苦しさ、筋肉のこわばりといった身体症状もよく見られます。
治療法
薬物療法としてはSSRIなどが用いられます。精神療法では、不安を客観的に見つめ、対処法を身につける認知行動療法などが有効です。リラクゼーション法(漸進的筋弛緩法や呼吸法など)で心身の緊張を和らげる練習も行います。
月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)
症状の特徴
 月経前の3〜10日間に起こる精神的・身体的な症状で、月経が始まると軽快または消失します。イライラ、気分の落ち込み、集中力低下、眠気、頭痛、乳房の張り、むくみなど、多様な症状が見られます。 月経前症候群の中でも特に精神症状が重く、日常生活に著しい支障をきたすものを月経前不快気分障害と言います。
月経前の3〜10日間に起こる精神的・身体的な症状で、月経が始まると軽快または消失します。イライラ、気分の落ち込み、集中力低下、眠気、頭痛、乳房の張り、むくみなど、多様な症状が見られます。 月経前症候群の中でも特に精神症状が重く、日常生活に著しい支障をきたすものを月経前不快気分障害と言います。
月経前症候群/月経前不快気分障害の抑うつ症状は、月経周期に関連して現れる点が特徴で、これにはホルモンバランスの変動が関与していると考えられています。
治療法
低用量ピルやSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などが治療に用いられることがあります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)
症状の特徴: 睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が一時的に止まったり(無呼吸)、浅くなったりする(低呼吸)ことを繰り返す病気です。その結果、睡眠の質が著しく低下し、長時間寝ても脳と体が休まらず、日中に会議中や運転中にも関わらず襲ってくるような強い眠気や、慢性的な倦怠感が生じます。家族に指摘される大きないびきや、起床時の頭痛(低酸素状態による血管拡張が原因)、口の渇き、集中力低下、気分の落ち込みなども特徴的なサインです。睡眠検査を行い診断します。
治療法
治療法は、重症度や原因により、CPAP療法(持続陽圧呼吸療法)、マウスピース、外科手術などがあります。
内分泌疾患
甲状腺機能低下性、甲状腺機能亢進症、クッシング病/症候群、慢性副腎皮質機能低下症、糖尿病といった内分泌疾患でも、倦怠感を伴うことがあります。経過や、特徴的な症状などからこれらの疾患が疑われる場合は、血液検査などの検査を行います。
その他の内科疾患
鉄欠乏性貧血、ビタミンB12欠乏症、葉酸欠乏症、神経疾患、悪性腫瘍(がん)、慢性疼痛性疾患(関節リウマチ、線維筋痛症、変形性関節症など)、感染症(慢性C型肝炎、HIV感染症/AIDSなど)、膠原病・自己免疫疾患、腎不全、といった疾患でもkん体感を伴うことがあります。
薬剤
 服用している薬剤の副作用として倦怠感が現れることがあります。原因薬剤の特定と、可能であれば代替薬への変更を検討します。
服用している薬剤の副作用として倦怠感が現れることがあります。原因薬剤の特定と、可能であれば代替薬への変更を検討します。
物質使用障害による抑うつ
アルコールや薬物の慢性使用により、倦怠感が現れます。物質の使用を中止することが治療の前提となります。