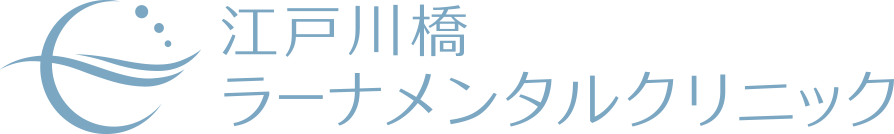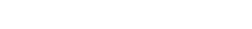- この記事のポイント
- 適応反応症(適応障害)とは
- 適応反応症(適応障害)の主な症状と特徴
- 適応反応症(適応障害)の原因として考えられていること
- 適応反応症(適応障害)はどのくらいの人が経験するのか
- 適応反応症(適応障害)の診断はどのように行われるのか
- 適応反応症(適応障害)の治療法
- 適応反応症のまとめ
この記事のポイント
- 適応反応症は、特定のストレスが原因で心身に不調が現れる状態であり、誰にでも起こりえます。
- 主な症状には、気分の落ち込み、不安、不眠、頭痛などがあり、日常生活に影響が出ることがあります。
- 治療の基本は、ストレスの原因を特定し、それを取り除くか軽減すること、そして十分な休養です。
Adjustment disorderは適応障害と訳されていましたが、最近は適応反応症と訳されています。ここでは適応反応症とし、見出しでは適応反応症(適応障害)とします。
適応反応症(適応障害)とは
適応反応症は、特定の出来事や状況によって生じる強いストレスに対して、心身が適応しきれなくなった状態を指します。医学的には、「明確に確認できるストレス因に対する反応として、そのストレス因の始まりから3ヶ月以内に情緒面または行動面の症状が出現する精神疾患」と定義されています。
この疾患を理解することは、自分自身の心身の状態を客観的に把握し、適切な対処法を見つけるための第一歩となります。本記事では、適応反応症の症状から治療法まで、分かりやすくお伝えします。
適応反応症(適応障害)の
主な症状と特徴
適応反応症では、精神面と身体面の両方にさまざまな症状が現れます。
精神症状
適応反応症の精神症状は多岐にわたります。代表的なものとしては以下のようなものがあります。
抑うつ気分
気分が沈み込み、何をしても楽しくない、悲しい気持ちが続く、涙もろくなるなど、うつ病と似た症状が現れることがあります。ただし、適応反応症の場合、ストレスの原因から離れると気分が改善することが多いという特徴があります。
不安感
特定の状況や出来事に対して過剰な心配や恐怖を感じたり、漠然とした不安が続いたりします。緊張感が高まり、落ち着きがなくなることもあります。
怒りや焦燥感
イライラしやすくなったり、些細なことでカッとなったり、焦る気持ちが強くなったりします。
集中力・判断力の低下
仕事や勉強に集中できない、物事を決められない、考えがまとまらないといった状態が見られます。
行動の変化
 人との交流を避けるようになったり、学業や仕事のパフォーマンスが低下したり、遅刻や欠席が増えたりすることがあります。また、衝動的な行動(例:過度な飲酒、無謀な運転など)が見られることも稀にあります。
人との交流を避けるようになったり、学業や仕事のパフォーマンスが低下したり、遅刻や欠席が増えたりすることがあります。また、衝動的な行動(例:過度な飲酒、無謀な運転など)が見られることも稀にあります。
これらの症状は、ストレスの原因となる出来事が始まってから早期に現れることが多いとされています。
身体症状:からだからのサインを見逃さない
こころの不調は、からだの症状としても現れることが少なくありません。
睡眠障害
寝つきが悪い(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、熟睡感がないなど、様々な睡眠の問題が生じます。
食欲の変化
食欲がなくなったり(食欲不振)、逆に食べ過ぎてしまったり(過食)することがあります。
疲労感・倦怠感
十分に休んでも疲れが取れない、体がだるい、気力が出ないといった症状です。
その他の身体症状
頭痛、肩こり、腹痛、吐き気、動悸、めまい、息苦しさなど、多様な症状が現れることがあります。
これらの身体症状は、内科などで検査をしても特に異常が見つからないことも多く、精神的なストレスが原因である可能性が考えられます。
日常生活や社会生活への影響
 上記のような精神症状や身体症状が続くことで、日常生活や社会生活に様々な支障が生じることがあります。
上記のような精神症状や身体症状が続くことで、日常生活や社会生活に様々な支障が生じることがあります。
例えば、仕事や学業の能率が著しく低下したり、家事や育児が手につかなくなったり、友人関係や家族関係が悪化したりすることが考えられます。趣味や楽しみにしていたことにも関心が持てなくなり、引きこもりがちになることもあります。
重要なのは、これらの変化が本人の怠慢や能力不足によるものではなく、ストレスに対する心身の反応として現れているという点です。
適応反応症(適応障害)の
原因として
考えられていること
適応反応症は、その名の通り、特定の「ストレス要因(ストレッサー)」に対する「適応」がうまくいかない状態です。まずストレス要因があり、さらにそこにいくつかの要因が絡み合って発症すると考えられています。
心理的要因
最も重要な要因は、明確に特定できるストレッサー(ストレス要因)の存在です。職場での過重労働、パワーハラスメント、配置転換、失業、結婚、離婚、出産、家族の病気や死、経済的困難など、人生の大きな変化や困難な出来事がストレッサーとなることがあります。
また、その人の性格傾向やストレスへの対処方法(コーピングスタイル)も関係しています。完璧主義の方や、他者への配慮を優先しがちな方は、ストレスを抱え込みやすい傾向があるとされています。
環境的・社会的要因
周囲のサポート体制の有無も重要な要因です。困難な状況に直面した時に、相談できる相手がいるか、理解してくれる人がいるかどうかは、適応反応症の発症や経過に大きく影響します。また、職場や学校の環境、家族関係、社会的な役割の変化なども関連しています。
生物学的要因
ストレスに対する身体の反応性には個人差があり、遺伝的な要因や体質的な要因も関与していると考えられています。
これらの環境的・社会的要因、心理的要因、そして生物学的要因が複雑に絡み合い、適応反応症の発症に至ると考えられています。
適応反応症(適応障害)は
どのくらいの人が
経験するのか
適応反応症は、決して珍しい疾患ではありません。一般人口における有病率は2〜8%程度と報告されており、精神科外来を受診する患者さんの中では5〜20%を占めるとされています。つまり、多くの方が人生のどこかで経験する可能性がある、身近な精神疾患といえます。
有病率
一般人口における適応反応症の有病率(ある時点でその病気にかかっている人の割合)は、調査対象や診断基準によって異なりますが、数パーセントから十数パーセントと報告されています。精神科医療の場面では、受診者の5%から20%が適応反応症と診断されるというデータもあります。これは、うつ病や不安症と並んで、決して稀な疾患ではないことを示しています。
好発年齢や発症しやすい時期
適応反応症は、特定の年齢層に限定されるものではなく、子どもから高齢者まで、あらゆる年代で発症する可能性があります。人生の転機や大きな環境変化が起こりやすい青年期や成人期初期に診断されることが多いという報告もありますが、これはその時期にストレスフルな出来事が集中しやすいためと考えられます。
性差
性差については、女性の方が男性よりも診断される割合が高いという報告がいくつかありますが、これは女性の方がストレスを自覚しやすく、医療機関を受診する傾向が高いことなどが影響している可能性も指摘されており、明確な結論は出ていません。
なりやすいとされる人の特徴やリスク要因(慎重な表現を心がける)
特定の性格や特徴を持つ人が必ず適応反応症になるわけではありませんが、一般的に以下のような場合にリスクが高まる可能性が指摘されています。
- 過去に精神的な問題を経験したことがある方
- ストレスへの対処能力が十分に育まれていないと感じる方
- 周囲にサポートしてくれる人が少ない(ソーシャルサポートが乏しい)方
- 経済的に困難な状況にある方
- 複数のストレッサーが同時に重なっている方
しかし、これらはあくまで統計的な傾向であり、これらの要因に当てはまらない人でも発症することはありますし、当てはまる人が必ず発症するわけでもありません。大切なのは、ご自身の状態を客観的に把握し、必要であれば専門家の助けを求めることです。
適応反応症(適応障害)の
診断はどのように行われるのか
診断基準について
精神科の診断では、国際的な診断基準が用いられます。代表的なものに、アメリカ精神医学会が作成した「DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル
第5版)」があります。DSM-5-TRにおける適応反応症の主な診断基準は以下の通りです。
- はっきりと確認できるストレス因子に反応して、そのストレス因子の始まりから3ヶ月以内に情動面または行動面の症状が出現する。
- これらの症状や行動は、臨床的に意味のあるものであり、それは以下のうち1つまたは両方の証拠がある。
- そのストレス因子に不釣り合いな程度の苦痛で、そのストレス因子の重症度や外的文脈、および文化的要因を考慮に入れても予測される範囲を超えている。
- 社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の重大な障害。
- このストレス関連障害は、他の精神疾患の基準を満たしておらず、すでに存在している精神疾患の単なる悪化でもない。
- 症状は、正常な死別反応を示すものではない。
- ストレス因子またはその結果が終結すれば、症状がその後さらに6ヶ月を超えて持続することはない。
これらの基準に基づいて、医師が総合的に判断します。ICD-11(国際疾病分類 第11版)でも同様の概念で定義されています。
診断のプロセス
診断は、主に以下のプロセスで行われます。
1問診
現在の症状、症状が現れた時期やきっかけ、生活状況、職歴、既往歴、家族歴などを詳しく伺います。特に、どのようなストレッサーが存在するのか、それがいつから始まり、どのように影響しているのかを丁寧に確認します。
2心理検査
必要に応じて、質問紙や作業を通して、心理状態や性格傾向、ストレスの度合いなどを客観的に評価するための心理検査を行うことがあります。
3身体的検査
身体症状が強い場合や、他の身体疾患の可能性が疑われる場合には、血液検査や画像検査などを行うこともあります。
4他の疾患との鑑別
うつ病、全般性不安症、パニック症、PTSD(心的外傷後ストレス障害)など、似た症状を示す他の精神疾患や、甲状腺機能異常などの身体疾患との鑑別を行います。
適応反応症(適応障害)の
治療法
 適応反応症の治療は、症状の改善だけでなく、生活の質(QOL)の向上と再発予防を目標として行われます。治療法は個人の状況に応じて選択され、多くの場合、複数のアプローチを組み合わせて行われます。
適応反応症の治療は、症状の改善だけでなく、生活の質(QOL)の向上と再発予防を目標として行われます。治療法は個人の状況に応じて選択され、多くの場合、複数のアプローチを組み合わせて行われます。
環境調整とストレス管理
適応反応症の治療において最も重要なのは、原因となっているストレス因を特定し、それを除去したり、軽減したりすることです。職場環境が原因の場合は、上司や人事部門との相談、業務量の調整、配置転換、必要に応じて休職などを検討します。家庭内の問題が原因の場合は、家族との話し合いや、必要に応じて別居などの環境調整を行うこともあります。
しかし、ストレス因を完全に除去することが難しい場合も多くあります。その場合は、ストレスとの付き合い方を学び、対処能力を高めることが重要になります。
精神療法・カウンセリング
精神療法は、適応反応症の治療において中心的な役割を果たします。認知行動療法では、ストレス状況に対する考え方や受け止め方を見直し、より適応的な思考パターンを身につけることを目指します。支持的精神療法では、患者さんの気持ちを受け止め、共感的に支えることで、心理的な安定を図ります。
問題解決療法では、現実的な問題解決のスキルを身につけ、ストレス状況に対処する能力を高めます。これらの療法を通じて、自分自身の感情や行動パターンを理解し、より健康的な対処法を身につけることができます。
薬物療法
適応反応症の治療において、薬物療法が中心となることは少ないですが、症状が強く、日常生活への支障が大きい場合には、症状を和らげる目的で補助的に用いられることがあります。副作用について心配される方も多いですが、医師と相談しながら適切に使用することで、比較的安全に症状の改善を図ることができます。
生活習慣の改善
規則正しい生活リズムの確立、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠など、基本的な生活習慣の改善も重要です。また、リラクゼーション法(深呼吸、筋弛緩法、瞑想など)を取り入れることで、日常的なストレスへの対処能力を高めることができます。
治療期間と回復の見通し
適応反応症の治療期間は、ストレス因の種類や強さ、本人の状態、治療への取り組み方などによって大きく異なります。一般的には、ストレス因が取り除かれれば、症状は数週間から数ヶ月で改善し、6ヶ月を超えて持続することはないとされています。しかし、ストレス因が持続する場合や、複数の問題を抱えている場合には、治療が長期にわたることもあります。焦らず、自分のペースで治療に取り組むことが大切です。
適応反応症のまとめ
ここまで、適応反応症の症状や原因、治療法について解説してきました。
適応反応症は、特定のストレスに対する心身の自然な反応であり、決してあなたの「弱さ」や「甘え」が原因ではありません。誰にでも起こりうることであり、適切な対処とサポートがあれば、多くの場合、症状は改善し、回復していくことができます。
もし、あなたが今、適応反応症かもしれないと感じていたり、つらい状況に悩んでいたりするなら、どうか一人で抱え込まず、勇気を出して専門機関に相談してみてください。当院では、常に最新の知見に基づいた医療を提供できるよう努めております。