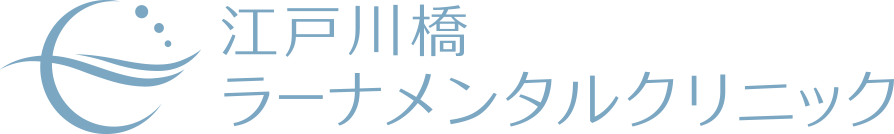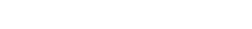- この記事のポイント
- 不安症(不安障害)について
- 不安症(不安障害)の主な症状と特徴
- 不安症の原因として考えられていること
- 不安症(不安障害)はどのくらいの人が経験するのか
- 不安症(不安障害)の診断
- 不安症(不安障害)の治療法
- よくある質問Q&A
- 不安症(不安障害)のまとめ
この記事のポイント
- 不安症は、日常生活に支障をきたすほどの強い不安や恐怖を感じる病気です。
- 原因は一つではなく、生物学的要因、心理的要因、環境的要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
- 早期の相談・治療が症状の悪化を防ぎ、回復への近道となります
Anxiety Disorderは不安障害と訳されていましたが、最近では不安症と訳されています。ここでは不安症とし、見出しでは不安症(不安障害)とします。
不安症(不安障害)について
「なんだかいつも不安で落ち着かない」「特定の状況になると、動悸や息苦しさを感じる」といった経験はありませんか? もしかしたら、それは不安症と呼ばれるこころの病気かもしれません。
不安症は、単なる「心配性」や「気の持ちよう」で片付けられるものではなく、過度の不安や恐怖が持続し、日常生活や社会生活に影響を与えます。不安症には全般性不安症、パニック症、広場恐怖症、社交不安症など、さまざまなタイプがあります。
不安症(不安障害)の
主な症状と特徴
不安症とは、日常生活に支障をきたすほどの過剰な不安や恐怖を感じる精神疾患の総称です。誰でも不安を感じることはありますが、不安症の場合、その不安が過度で持続的であり、日常生活に大きな影響を与えます。以下に代表的な不安症について詳しく説明します。
全般性不安症(全般性不安障害)
 全般性不安症は、特定の対象に限らず、日常のさまざまな出来事や活動に対して、過度な心配や不安が慢性的に続く状態です。仕事、健康、家族、経済状況など、あらゆるものが心配の対象となり、その不安を自分でコントロールすることが困難になります。
全般性不安症は、特定の対象に限らず、日常のさまざまな出来事や活動に対して、過度な心配や不安が慢性的に続く状態です。仕事、健康、家族、経済状況など、あらゆるものが心配の対象となり、その不安を自分でコントロールすることが困難になります。
症状
- 精神症状:持続的な不安感、緊張感、イライラ感、集中力低下、落ち着きのなさ、過敏性など
- 身体症状:筋肉の緊張、疲労感、頭痛、動悸、発汗、震え、睡眠障害(入眠困難、中途覚醒)、消化器系の不調(胃痛、下痢)など
特徴
- 些細なことでも過剰に心配し、悪い結果ばかりを考えてしまう。
- 常に緊張しており、リラックスできない。
- 不安のために仕事や家事に集中できない。
- 予期不安が強く、まだ起こっていないことまで心配してしまう。
パニック症(パニック障害)
パニック症は、突然激しい恐怖感や不安感が襲い、動悸、発汗、震え、息切れ、胸痛、めまい、「死ぬのではないか」という強い恐怖感などのパニック発作が起こる病気です。パニック発作は数分間続き、その後は疲労感や脱力感が残ることがあります。
症状
- 激しい動悸、心臓がドキドキする
- 呼吸困難、息苦しさ、窒息感
- めまい、ふらつき、気が遠くなる感じ
- 発汗、震え、体の痺れ
- 胸痛、胸部の圧迫感
- 吐き気、腹部の不快感
- 現実感の喪失、自分が自分でないような感じ
- 死への恐怖、気が狂ってしまうのではないかという恐怖
特徴
- パニック発作は、場所や状況に関係なく突然起こる。
- 発作を繰り返すうちに、「また発作が起こるのではないか」という予期不安が強くなり、日常生活に支障をきたすようになる。
広場恐怖症
 広場恐怖症は、逃げ場がない、助けが得られないと感じる場所や状況に対して強い不安や恐怖を感じる病気です。具体的には、公共交通機関(電車、バスなど)、広い場所(デパート、駐車場など)、閉鎖空間(エレベーターなど)、人混みなどが挙げられます。
広場恐怖症は、逃げ場がない、助けが得られないと感じる場所や状況に対して強い不安や恐怖を感じる病気です。具体的には、公共交通機関(電車、バスなど)、広い場所(デパート、駐車場など)、閉鎖空間(エレベーターなど)、人混みなどが挙げられます。
症状
- 広場や特定の場所・状況に対して強い不安や恐怖を感じる。
- パニック発作を伴うことが多い。
特徴
- その場所や状況を避けるようになる。
- 重症の場合は、外出自体が困難になり、家に引きこもりがちになる。
社交不安症(社交不安障害)
社交不安症は、他人から注目される社会的状況で強い不安や恐怖を感じる病気です。人前での発表、食事、会話、初対面の人との交流などが極度に苦手になります。
症状
- 人前で話すこと、発表することに対する強い不安や恐怖
- 他人と目を合わせることへの抵抗
- 人前で食事をすることへの不安
- 初対面の人と話すことへの緊張
- 赤面、発汗、震えなどの身体症状
- 恥をかくこと、批判されることへの強い恐れ
特徴
- 単なる「人見知り」とは異なり、日常生活に支障をきたすほどの強い不安を感じる。
- 社交的な場面を避けるようになるため、人間関係や社会生活に影響が出ることがある。
不安症の原因として
考えられていること
不安症の原因は、単一のものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
生物学的要因
脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、GABAなど)のバランスの乱れが、不安障害の発症に関与していることが分かっています。また、遺伝的な要因も一定程度関係しており、家族に不安症の方がいる場合、発症リスクがやや高くなることが知られています。ただし、これは「必ず発症する」という意味ではありません。
心理的・環境的要因
色々な体験、慢性的なストレス、大きなライフイベント(転職、結婚、出産など)が引き金となることがあります。また、完璧主義的な性格傾向や、物事を悲観的に捉えやすい思考パターンも、不安症の発症や維持に関わることがあります。
不安症(不安障害)は
どのくらいの人が
経験するのか
全般性不安症
有病率
- 生涯有病率は、米国で約9%、日本では約3%と報告されていますが、実際にはもっと多い可能性も指摘されています。
- 1年有病率は約3%という報告もあります。
発症年齢
発症年齢の中央値は30歳とされていますが、青年期から中年以降まで幅広く、思春期以前の発症は稀です。
性差
- 女性は男性の約2倍発症しやすいとされています。
その他
- 慢性的に経過することが多く、完全寛解率は低いとされています。
- 男性ではアルコールなどの物質依存との関連が指摘されることがあります。
パニック症
有病率
- 1年有病率は3~4%程度とされています。
- 生涯有病率は、日本では約0.8%という報告があります。
発症年齢
典型的な発症年齢は20代前半です。小児期や40代以降の発症は比較的まれです。
性差
女性に多く、男女比は1対2~3とされています。
その他
- 症状の増悪と軽快を繰り返し、慢性的な経過をたどることがあります。
- 他の不安症、うつ病、双極症、依存症などを併存しやすい傾向があります。
- 約半数の患者がうつ状態やうつ病を併発するという報告もあります。
広場恐怖症
有病率
- 約2%の人に見られるとされています。
発症年齢
- パニック症が先行しない場合の平均発症年齢は25~29歳ですが、全体の発症年齢の中央値は17歳という報告もあります。青年期や若い成人が発症することが多いですが、高齢者での発症も見られます。
性差
- 女性に多い傾向があります。
その他
- 持続性・慢性に経過することが多いです。
- 他の不安症群(パニック症、社交不安症、限局性恐怖症)、うつ病、アルコール使用障害などを合併しやすいです。
社交不安症
有病率
- 米国の12ヶ月有病率は約6.8%、生涯有病率は約12.1%と報告されています。
- 日本のWHOによる疫学調査では、12ヶ月有病率は0.8%と報告されており、欧米と比較して低い傾向にあります。これは文化的な背景も影響している可能性があります。
発症年齢
- 発症年齢は平均13歳と比較的若く、10代半ばに多いとされています。
性差
- 女性は男性より2倍程度発症しやすいという報告がありますが、男女差は特にないとされる報告もあります。
その他
- 受診率が低いことが指摘されており、治療を受けない場合、症状が数年以上持続することがあります。
- アルコール乱用のリスクが高いとされています(特に女性)。
不安症(不安障害)の診断
以下に、代表的な不安症である「全般性不安症」「パニック症」「広場恐怖症」「社交不安症」の診断プロセスを、DSM-5の基準に触れながら解説します。
全般性不安症(全般性不安障害)
DSM-5に基づく診断のポイント
以下の特徴が診断の際に重視されます。
- 過剰な不安と心配:仕事や健康など、多数の出来事または活動についての過剰な不安と心配が、少なくとも6ヶ月間、ない日よりもある日の方が多い。
- コントロール困難:その心配を自分でコントロールすることが難しいと感じる。
- 身体・認知症状:以下の6つの症状のうち、3つ(子どもの場合は1つ)以上が存在する。
- 落ち着きがない、緊張感、過敏な感じ
- 疲れやすい
- 集中できない、心が空白になる
- 怒りっぽい
- 筋肉の緊張
- 睡眠障害(入眠困難、中途覚醒、熟眠感の欠如)
- 臨床的に意味のある苦痛または機能の障害:症状によって、社会的、職業的、または他の重要な領域で著しい苦痛や機能の障害を引き起こしている。
- 除外診断:症状が、薬物(例:カフェインの過剰摂取)や医薬品、他の身体疾患(例:甲状腺機能亢進症)によるものではない。また、他の精神疾患(例:パニック症における「また発作が起きるか」という心配)ではうまく説明できない。
パニック症(パニック障害)の診断
DSM-5に基づく診断のポイント
- 予期しないパニック発作の反復:パニック発作とは、動悸、発汗、震え、息苦しさ、胸痛、吐き気、めまい、死ぬことへの恐怖など、強い恐怖と共に複数の身体・認知症状が突然出現し、数分でピークに達する状態を指します。パニック症の診断には、この発作が「予期せず」に起こることが重要です。
- 発作後の持続的な懸念または行動の変化:少なくとも1回の発作の後、以下のうち1つ以上が1ヶ月以上続く。
- 予期不安:さらなるパニック発作やその結果(心臓発作で死ぬ、気が狂うなど)についての持続的な心配。
- 不適応的な行動変化:発作を避けるための行動(例:運動や慣れない場所に行くのをやめる)。
- 除外診断:症状が、薬物や身体疾患(例:心疾患、前庭機能障害)によるものではない。また、他の精神疾患(例:社交不安症の人が注目される場面でだけ発作を起こす)ではうまく説明できない。
広場恐怖症
DSM-5に基づく診断のポイント
- 特定の状況への恐怖:以下の5つの状況のうち、2つ以上に対して著しい恐怖や不安を感じる。
- 公共交通機関の利用(例:バス、電車、飛行機)
- 広い場所にいること(例:駐車場、橋の上)
- 囲まれた場所にいること(例:店、劇場、映画館)
- 列に並ぶ、または群衆の中にいること
- 一人で家の外にいること
- 恐怖の理由:これらの状況を恐れる理由は、「もしパニック様の症状や、その他の耐え難い症状(例:高齢者における転倒、失禁)が起きた場合に、脱出が困難であったり、助けが得られないかもしれない」という考えにある。
- 回避行動:これらの状況を積極的に避けたり、誰かの同伴を求めたり、強い恐怖や不安を感じながら耐え忍んだりする。
- 持続期間:恐怖、不安、回避が通常6ヶ月以上続く。
- 除外診断:恐怖の対象が、他の精神疾患でよりよく説明されないこと(例:社交不安症における社交場面の回避とは異なる)。
社交不安症(社交不安障害)
DSM-5に基づく診断のポイント
- 社交状況への恐怖:他者から注視される可能性のある1つ以上の社交状況(例:雑談、人前での食事や発表、会議での発言)に対する著しい恐怖や不安。
- 否定的な評価への恐怖:自分が恥をかいたり、屈辱的な言動をしたり、不安症状(赤面、震え、発汗など)を見せたりすることで、他者から否定的に評価されることを恐れる。
- 状況と恐怖の関連:その社交状況は、ほとんど常に恐怖や不安を引き起こす。
- 回避行動: その社交状況を積極的に避けたり、強い恐怖や不安を感じながら耐え忍んだりする。
- 不釣り合いな恐怖:その恐怖や不安は、実際の社会的状況の脅威や、社会文化的な背景から考えて不釣り合いなものである。
- 持続期間:恐怖、不安、回避が通常6ヶ月以上続く。
- 限定:恐怖がスピーチやパフォーマンスの状況に限定される場合は、「パフォーマンス限局型」と特定される。
これはあくまで診断基準の一例であり、実際の診断は医師が総合的に判断します。
不安症(不安障害)の治療法
薬物療法
不安症の薬物療法では、主に抗うつ薬(SSRI、SNRIなど)や抗不安薬が使用されます。これらの薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えることで、不安症状を和らげる効果があります。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)
これらは、不安症治療の中心となることが多い抗うつ薬の一種です。効果が現れるまでに数週間かかることがありますが、比較的副作用が少なく、長期的な使用にも適しています。
ベンゾジアゼピン系抗不安薬
即効性があり、強い不安やパニック発作を一時的に抑える効果があります。しかし、眠気、ふらつきなどの副作用や、長期使用による依存のリスクがあるため、短期間の使用や頓服が推奨されます。
その他の薬剤
タンドスピロン(セロトニン1A受容体作動薬)などが用いられることもあります。また社交不安症ではβ遮断薬(動悸や震えを抑える)を使用することがあります。
精神療法
認知行動療法(CBT)は、不安症に対して用いられる精神療法です。不安を引き起こす考え方のパターンを見直し、より現実的で建設的な考え方を身につけていきます。また、段階的に不安を感じる状況に慣れていく暴露療法も効果的です。
生活改善とセルフケア
規則正しい生活リズム、適度な運動、バランスの良い食事は、不安症状の改善に役立ちます。特に、有酸素運動は不安を軽減する効果があることが科学的に証明されています。また、深呼吸法、筋弛緩法、マインドフルネスなどのリラクゼーション技法も、日常的に実践することで不安をコントロールしやすくなります。
カフェインやアルコールの摂取を控えめにすることも大切です。これらは一時的に不安を和らげるように感じられても、長期的には不安を悪化させる可能性があります。
治療期間は個人差がありますが、少し時間がかかることも多く、長い方ですと、年単位の治療になることも珍しくありません。焦らず、自分のペースで治療に取り組むことが大切です。
よくある質問(Q&A)
身体的な検査で異常が見つからない場合、不安症が背景にある可能性があります。不安が強くなると、自律神経のバランスが乱れ、動悸、息苦しさ、発汗、震えなどの身体症状が現れます。これは命に関わるものではありませんが、本人にとっては非常につらい体験です。
これらの症状は、不安や恐怖を感じた時に身体が「危険だ」と反応して起こるものです。本来は生命を守るための反応ですが、実際には危険がない状況でこの反応が起こってしまうと、日常生活に支障をきたすことになります。
「このまま死んでしまうのではないか」「気が狂ってしまうのではないか」といった強い恐怖を伴うことが特徴です。パニック発作は1年間で成人の約11%が経験するとされており、決して珍しいものではありません。ただし、発作を経験しても、多くの方は治療なしで回復します。
一方、広場恐怖症は、助けを得たり逃げることが困難な状況や場所に対する恐怖と回避行動が中心です。パニック発作を伴う場合もありますが、必ずしもパニック発作がなくても診断されることがあります。実際には、広場恐怖症の30~50%の方がパニック症を併発しているとされ、両者は重なり合うことが多い疾患です。
「些細なことでも悪い方向に考えてしまう」「心配が頭から離れない」といった特徴があり、落ち着きのなさや緊張感、疲れやすさ、集中困難、イライラしやすさ、筋肉の緊張、睡眠障害などの症状が現れます。広場恐怖症やパニック症のように特定の状況に限定された不安ではなく、日常的に続く不安と緊張が中心となります。
重要なのは、これらの状況で「もしパニック発作や耐え難い症状が出たら、逃げられない、助けを求められない、恥ずかしい思いをする」という予期が不安の中心にあることです。
この予期不安があるために、発作が起きそうな場所や状況を避ける「回避行動」につながります。予期不安と回避行動は悪循環を形成し、避ければ避けるほど恐怖は強まり、行動範囲は狭まっていきます。
一方、パニック発作そのものは、1年間で成人の約11%が経験するとされており、かなり高い割合です。ただし、発作を経験しても、多くの方は治療なしで回復し、パニック症に進行するのは一部です。
また、本来は危険を知らせる役割を持つ脳の「アラーム機構」が誤作動を起こしているという仮説もあります。心理的要因としては、過去のストレスフルな出来事や、不安になりやすい気質が関係している可能性があります。遺伝的要因も関与しており、多くの場合これらの複数の要因が重なり合って発症すると考えられています。
性格については、悲観的や内省的な性格、周りに過剰に合わせてしまう他者配慮性の高さなどが指摘されていますが、特定の性格だけが原因とは言えません。重要なのは、現在のところ直接の原因は脳内の神経伝達物質の分泌の乱れにあるとされており、「気持ちの持ちよう」や「性格の問題」として片付けるべきではないということです。
広場恐怖症は、20代前後と40歳前後の2つのピークがあるとされています。ただし、これらはあくまで統計的な傾向であり、個人差は大きいものです。どの年齢であっても発症する可能性はありますし、年齢によって治療効果に大きな差があるわけではありません。
息苦しさがある場合は、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患も考慮されます。また、甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では、動悸、発汗、手の震え、体重減少などの症状が現れ、パニック発作と似た症状を示すことがあります。医療機関では、まずこれらの身体疾患を除外するための検査を行います。
パニック症では、約半数の方がうつ病を合併するとされています。慢性的な予期不安や回避行動により生活が制限され、それが抑うつ状態につながることがあります。治療を受けずに放置すると、アルコール依存症になるリスクも指摘されています。
また、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、即効性があるため発作時の頓服や治療初期に使用されることがあります。ただし、依存のリスクがあるため、長期使用は避け、症状が改善したら減量していきます。
それは誤った認知、つまり誤った考え方や認識が、予期不安や広場恐怖を起こしている原因になっているためです。特に広場恐怖症では、回避している状況に少しずつ挑戦していく「曝露療法」が効果的とされています。最終的には「自分で自分の治療者になる」ことを目標として、治療を行います。
薬物療法を開始すると、徐々にパニック発作の頻度が減り、日常生活が送りやすくなってきます。ただし、予期不安や広場恐怖といった症状が完全に改善するまでには、さらに時間がかかることがあります。症状が改善しても再発予防のため、通常は約1年間は薬の内服を継続することが勧められます。
重症の場合や、広場恐怖が強く生活範囲が著しく制限されている場合は、治療期間が長期に及ぶこともあります。一人ひとりの状態や回復のペースは異なりますので、焦らず自分のペースで治療を続けることが大切です。
また、慢性化するとうつ病やアルコール依存症などの二次的な問題を引き起こすリスクが高まります。一方、早期に適切な治療を開始すれば、多くの方で症状の改善が期待できます。不安症は脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが関与している疾患であり、適切な薬物療法と認知行動療法を組み合わせることで、効果的に症状を改善できます。
また、うつ気分が続く、眠れない日が続く、アルコールに頼るようになった、という場合も早めの受診が望ましいでしょう。症状の強さや持続期間に関わらず、「これは普通ではない」と感じたり、生活の質が低下していると感じたりする場合は、早めに相談することが重要です。
不安症(不安障害)のまとめ
 不安症は、治療せずにいると徐々に悪くなっていくことが多いです。「我慢すればいいだけだから」「避ければいいだけだから」と放っておいて、気がついたら悪化していた、とならないように早めの受診をおすすめします。
不安症は、治療せずにいると徐々に悪くなっていくことが多いです。「我慢すればいいだけだから」「避ければいいだけだから」と放っておいて、気がついたら悪化していた、とならないように早めの受診をおすすめします。
受診をためらう気持ちはよく分かります。「こんなことで受診してもいいのか」「自分の我慢が足りないだけでは?」そんな風に感じているかもしれません。しかし、症状に悩んでいるなら、それは十分に受診の理由になります。それぞれに合った最善の治療法を一緒に考え、安心して治療に取り組めるようサポートします。一人で悩まず、専門家の力を借りて、回復への第一歩を踏み出してみませんか。