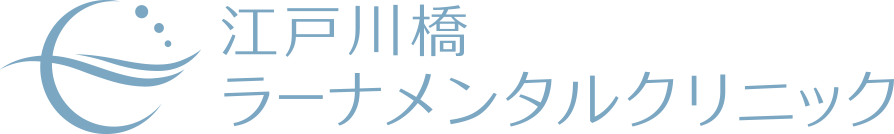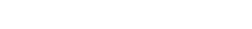- この記事の要点
- 双極症(双極性障害)とは
- 双極症(双極性障害)の主な症状と特徴
- 双極症(双極性障害)の原因として考えられていること
- 双極症(双極性障害)はどのくらいの人が経験するのか
- 双極症(双極性障害)の診断はどのように行われるのか
- 双極症(双極性障害)の治療法
- 双極症(双極性障害)のまとめ
この記事の要点
- 双極症は躁状態とうつ状態を繰り返す疾患で、どちらの状態も日常生活に大きな影響を与えます。
- 治療は薬物療法を中心に、精神療法や生活リズムの調整を組み合わせて行い、長期的な視点でじっくりと取り組むことが大切です。
- 双極症は100人に1~2人が経験する疾患であり、専門医による早期の診断と治療により、多くの方が充実した人生を送っています。
Bipolar Disorderは双極性障害と訳されていましたが、最近は双極症と訳されています。ここでは双極症とし、見出しでは双極症(双極性障害)とします。
双極症(双極性障害)とは
 双極症は、かつて「躁うつ病」と呼ばれていた精神疾患です。気分が異常に高揚する「躁状態」または「軽躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」を繰り返すことが特徴です。単なる気分の浮き沈みとは異なり、日常生活に大きな影響を与えます。
双極症は、かつて「躁うつ病」と呼ばれていた精神疾患です。気分が異常に高揚する「躁状態」または「軽躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」を繰り返すことが特徴です。単なる気分の浮き沈みとは異なり、日常生活に大きな影響を与えます。
この記事では、双極症の症状や原因、治療法について、医学的に正確な情報を分かりやすくお伝えします。
双極症(双極性障害)の主な症状と特徴
双極症の最大の特徴は、躁状態とうつ状態という対照的な気分の変化を繰り返すことです。
躁状態・軽躁状態の症状
躁状態は、気分が異常に高揚し、エネルギーに満ち溢れているように見える状態です。本人は爽快感を感じていることもありますが、周囲から見ると普段とは違う、行き過ぎた行動が目立つことがあります。軽躁状態は、躁状態よりも程度が軽いものの、普段のその人とは異なる高揚感が数日間以上続く状態を指します。
精神症状(思考、感情、行動面の変化など)
- 気分の高揚:異常に陽気になったり、多幸感に包まれたりします。些細なことで興奮しやすく、怒りっぽくなることもあります。
- 思考の奔逸(ほんいつ):次から次へと考えが湧き出て、話がまとまらなくなります。アイデアが豊富に出るように感じますが、現実的でないことが多いです。
- 誇大妄想(こだいもうそう):自分には特別な才能や力がある、偉大な人物だなどと思い込むことがあります。
- 注意散漫:周囲の刺激にすぐに気が散り、一つのことに集中できなくなります。
- 多弁・多動:いつもより口数が増え、早口になったり、じっとしていられず動き回ったりします。
- 睡眠欲求の減少:数時間しか眠らなくても平気になったり、全く眠らなくても元気だと感じたりします(例:「ショートスリーパーになった」と感じる)。
- 判断力の低下・衝動的な行動:後先を考えずに高額な買い物をしたり、危険な行動をとったり、性的逸脱行動が見られたりすることがあります。社交性が増し、初対面の人にも過度に馴れ馴れしくなることもあります。
身体症状
躁状態では、身体的な疲労を感じにくくなるため、休息を取らずに活動し続けることがあります。その結果、体重が減少することもあります。
日常生活や社会生活への影響
躁状態にあるときは、本人は調子が良いと感じていることが多く、病識(自分が病気であるという認識)を持ちにくい傾向があります。そのため、周囲の忠告を聞き入れず、人間関係のトラブル(喧嘩、暴力など)や社会的な信用失墜(借金、仕事上の大きな失敗など)、法的な問題を引き起こしてしまうことがあります。軽躁状態の場合、本人も周囲も「いつもより調子が良い」「活動的だ」と肯定的に捉えがちですが、やはり判断力の低下から思わぬ失敗を招くこともあります。
うつ状態の症状
うつ状態は、躁状態とは対照的に、気分が深く沈み込み、何事にも興味や喜びを感じられなくなる状態です。
精神症状(思考、感情、行動面の変化など)
- 抑うつ気分:気分が落ち込み、悲しい、虚しい、絶望的だと感じます。
- 興味・喜びの喪失:以前は楽しめていた活動に対しても興味が持てず、喜びを感じられなくなります(例:趣味や娯楽を楽しめない)。
- 思考力・集中力の低下:物事を考えたり、決断したりすることが難しくなります。集中力が続かず、仕事や家事が手につかなくなります。
- 自責感・無価値感:自分を過度に責めたり、自分には価値がないと感じたりします。
- 希死念慮(きしねんりょ)・自殺企図:生きているのがつらいと感じ、死にたいと考えたり、実際に自殺を試みたりすることがあります。
- 行動の抑制:口数が減り、動きが緩慢になります。人と会うのが億劫になり、引きこもりがちになることもあります。
身体症状
- 睡眠障害:寝付けない(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)などの不眠症状や、逆に眠りすぎてしまう過眠症状が現れることがあります。
- 食欲の変化:食欲がなくなって体重が減少したり、逆に食欲が増して体重が増加したりすることがあります。
- 易疲労感・倦怠感:体が重く、非常に疲れやすくなります。常にだるさを感じ、気力が湧きません。
- その他:頭痛、肩こり、動悸、めまい、便秘、下痢などの身体的な不調が現れることもあります。
日常生活や社会生活への影響
うつ状態では、学業や仕事の能率が低下してしまいます。家事や身の回りのことができなくなり、日常生活に支障をきたします。
双極症(双極性障害)の原因として考えられていること
双極症の原因は、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
脳の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなど)のバランスの乱れや、脳の特定部位の機能変化が関与しています。遺伝的要因も重要ですが、遺伝的素因があっても必ず発症するわけではありません。
強いストレスや大きなライフイベント、不規則な生活リズム、特に睡眠リズムの乱れも症状の発症や悪化に関連します。重要なのは、双極症は「性格の問題」や「心の弱さ」が原因ではなく、生物学的な脆弱性を持つ人が心理的・環境的ストレスにさらされたときに発症しやすくなる医学的な状態だということです。
双極症(双極性障害)はどのくらいの人が経験するのか
 双極症の生涯有病率は約1~2%で、100人に1~2人は生涯のうちに経験する可能性があります。発症年齢は10代後半から20代前半が多く、平均は25歳前後です。性別による大きな差はありませんが、女性では産後に発症や悪化することがあります。
双極症の生涯有病率は約1~2%で、100人に1~2人は生涯のうちに経験する可能性があります。発症年齢は10代後半から20代前半が多く、平均は25歳前後です。性別による大きな差はありませんが、女性では産後に発症や悪化することがあります。
双極症の「なりやすさ」には、前述した遺伝的要因が関与していると考えられています。血縁者に双極症の方がいる場合は、発症リスクが一般よりも高まることが分かっています。
しかし、これはあくまで統計的な傾向であり、遺伝的要因だけで発症が決まるわけではありません。多くの場合、遺伝的な素因に、ストレスや生活習慣の乱れといった環境要因が複雑に絡み合って発症に至ると考えられています。
双極症(双極性障害)の診断はどのように行われるのか
双極症の診断は、医師による詳しい問診と症状評価が中心です。
主な診断基準
診断にはDSM-5-TRなどの国際的基準が用いられます。
例えば、DSM-5-TRにおける躁エピソードの診断基準の概要は以下の通りです(簡略化しています)。
- 気分が異常かつ持続的に高揚し、開放的または易怒的となる。加えて、異常にかつ持続的に亢進した、目標指向性の活動または活力。これらの期間が、少なくとも1週間、ほぼ毎日、1日の大部分で持続する(入院が必要な場合はいかなる期間でもよい)。
- 気分の障害の期間中、以下の症状のうち3つ(またはそれ以上)(気分が易怒的な場合は4つ)が有意の程度に認められ、普段の行動とは明らかに異なっている。
- 自尊心の肥大、または誇大
- 睡眠欲求の減少(例:3時間眠っただけで十分な休息が得られたと感じる)
- 普段より多弁であるか、しゃべり続けようとする切迫感
- 観念奔逸、またはいくつもの考えが競い合っているという主観的な体験
- 注意散漫(すなわち、注意があまりにも容易に、重要でないまたは関係のない外的刺激によって転導される)が報告されるか、または観察される
- 目標指向性の活動(社会的、職場または学校内、性的のいずれか)の増加、または精神運動焦燥(すなわち、目的のない非目標指向性の活動)
- 困った結果を招く可能性が高い活動に熱中すること(例:抑制のきかない買いあさり、性的無分別、またはばかげた事業への投資などに耽る)
- 気分の障害は、職業的機能に著しい障害を引き起こしている、または社会的活動もしくは他者との人間関係に著しい障害を引き起こしている、あるいは自分自身または他人に害を及ぼすことを防ぐために入院が必要であるほど重篤である。
- エピソードは、物質(例:乱用薬物、医薬品、他の治療)の直接的な生理学的作用、または他の医学的状態によるものではない。
次に、DSM-5-TRにおける抑うつエピソード(うつ状態)の診断基準の概要は以下の通りです(簡略化しています)。- 以下の症状のうち5つ(またはそれ以上)が同じ2週間の期間中に存在し、病前の機能からの変化を示しており、そのうち少なくとも1つは(1)抑うつ気分または(2)興味または喜びの喪失である。
- 抑うつ気分がほとんど1日中、ほとんど毎日続く(例:悲しい、空虚な、絶望的な感じがする、または涙ぐんでいるように見える)。
- ほとんどすべての活動における興味または喜びの著しい減退がほとんど1日中、ほとんど毎日続く。
- 食事療法をしていないのに、有意の体重減少、または体重増加(例:1カ月で体重の5%以上の変化)、またはほとんど毎日の食欲の減退または増加。
- ほとんど毎日の不眠または過眠。
- ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止(他者によって観察可能なもの、単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではない)。
- ほとんど毎日の易疲労感、または気力の減退。
- ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感(妄想的であるかもしれないもので、単に自分をとがめること、または病気になったことに対する罪悪感ではない)。
- 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日認められる(主観的な訴えによるものか、他者の観察によるもの)。
- 死についての反復的な思考(死の恐怖だけではない)、特別な計画はないが反復的な自殺念慮、または自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。
- その症状は、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
- そのエピソードは、物質の直接的な生理学的作用、または他の医学的状態によるものではない。
- 抑うつエピソードの症状は、統合失調感情障害、統合失調症、統合失調症様障害、妄想性障害、または他の特定および不特定の統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群によってはうまく説明されない。
- これまでに躁病エピソードまたは軽躁病エピソードが存在したことがない。(このE項目は、大うつ病性障害の診断基準であり、双極症のうつ状態の診断では考慮の仕方が異なります。双極症の場合は、過去に躁エピソードまたは軽躁エピソードの既往があることが前提となります。)
診断のプロセス
現在の症状や過去の気分変化の詳しい聞き取り、家族歴の確認、他の疾患との鑑別診断が行われます。必要に応じて血液検査や心理検査も実施されます。
双極症(双極性障害)の治療法
双極症の治療は、症状改善、再発予防、生活の質向上を目指して行われます。
薬物療法
 気分安定薬(リチウム、バルプロ酸、カルバマゼピン、ラモトリギンなど)や非定型抗精神病薬(オランザピン、リスペリドン、クエチアピン、アリピプラゾールなど)が治療薬になります。病状に応じて、それぞれの薬の特徴を考慮し選択していきます。効果が現れるまで時間がかかったり、副作用も出ることがあるので、適宜調整や変更をしながら治療を進めていきます。
気分安定薬(リチウム、バルプロ酸、カルバマゼピン、ラモトリギンなど)や非定型抗精神病薬(オランザピン、リスペリドン、クエチアピン、アリピプラゾールなど)が治療薬になります。病状に応じて、それぞれの薬の特徴を考慮し選択していきます。効果が現れるまで時間がかかったり、副作用も出ることがあるので、適宜調整や変更をしながら治療を進めていきます。
精神療法
認知行動療法、対人関係・社会リズム療法、心理教育などが効果的です。家族療法やグループ療法も、回復を促進します。
生活改善
規則正しい睡眠リズム、適度な運動、バランスの良い食事、ストレスマネジメントが重要です。気分日記をつけることで自己理解が深まります。
双極症(双極性障害)のまとめ
双極症は診断までに時間を要すことも多く、また、回復への道のりは人それぞれですが、治療にも時間を要することが多く、総じてじっくりと取り組むことが大事になる疾患です。
当院では、それぞれに合った最善の治療法を一緒に考え、安心して治療に取り組めるようサポートします。困り事があれば、一度相談をしてみてください。