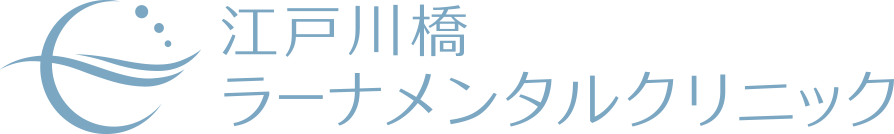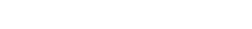あがり症(パフォーマンス限局型社交不安症)の疫学 ~「あがり症」でお悩みの方へ~
1. はじめに
- ✔「プレゼンの時だけ極度に緊張する」といった悩みは、治療可能な疾患の可能性があります。
- ✔多くの方が「性格の問題」と考え一人で抱え込みがちですが、適切な治療で改善が期待できます。
「プレゼンの時だけ極度に緊張する」「会議での発言が怖い」「人前で発表する場面になると頭が真っ白になる」――このような悩みを抱えている方は、実は少なくありません。一般的に「あがり症」と呼ばれるこの状態は、医学的には「パフォーマンス限局型社交不安症」という治療可能な疾患である可能性があります。
多くの方が「あがり症は性格の問題」「慣れれば治る」と考えて一人で抱え込んでいますが、実は適切な治療により改善が期待できるのです。
2. 「あがり症」とパフォーマンス限局型社交不安症
- ✔症状が半年以上続き、学業や仕事に支障をきたす場合、単なる性格の問題ではない可能性があります。
- ✔重度のあがり症は、医学的に「パフォーマンス限局型社交不安症」と診断され、治療の対象となります。
あがり症は病気なのか?
一般に「あがり症」と呼ばれる状態には、さまざまな程度があります。誰でも人前では多少緊張するものですが、以下のような状態が半年以上続き、学業や仕事に支障をきたしている場合、それは単なる性格の問題ではなく、治療可能な疾患である可能性があります:
- ・人前で話すときに動悸や震えが強く、声が出なくなる
- ・発表の数日前から不安で眠れない、食欲がなくなる
- ・重要なプレゼンや発表を避けるようになり、キャリアに影響が出ている
- ・準備に異常なほど時間をかけ、日常生活に支障が出ている
このような状態は、医学的にはパフォーマンス限局型社交不安症と診断されることがあります。つまり、重度のあがり症は、適切な治療の対象となる疾患なのです。
日本では、このような症状を「あがり症」と呼ぶことが一般的です。しかし「あがり症」という言葉は医学用語ではなく、また「性格の問題」「気合いで何とかなる」といった誤解を招きやすい側面があります。
そのため医療機関では、国際的な診断基準に基づき「パフォーマンス限局型社交不安症」という診断名を用います。ただし、患者さんとの会話では「いわゆるあがり症のことです」と説明することも多く、両者は基本的に同じ状態を指していると考えて差し支えありません。
3. どのくらいの人が「あがり症」で悩んでいるのか
- ✔社交不安症は生涯で約8~10人に1人が経験する、決して珍しくない疾患です。
- ✔年間有病率はうつ病とほぼ同程度であり、特別なものではありません。
実は多くの人が同じ悩みを抱えています
社交不安症全体の生涯有病率は約7~13%と報告されており、約8~10人に1人が人生のどこかで経験する計算になります¹⁾²⁾。その中で、あがり症(パフォーマンス限局型)に分類される方は約20~30%程度と報告されています³⁾⁴⁾。
つまり、「人前で話すときだけ極度にあがる」という悩みを持つ方は、決して珍しくないのです。
主要な精神疾患の年間有病率(米国)
| 疾患名 | 有病率 |
|---|---|
| 不安障害全体 | 19.1% |
| 社交不安症 | 7.1% |
| うつ病 | 8.3% |
| パニック障害 | 2.7% |
| 双極性障害 | 2.8% |
| 統合失調症 | 1%未満 |
この表が示すように、社交不安症は年間有病率7.1%と、不安障害の中では特定の恐怖症に次いで2番目に多い疾患です。また、うつ病(8.3%)とほぼ同程度の頻度であり、統合失調症や双極性障害と比較すると、はるかに多くの方が経験する疾患であることがわかります。決して特別なものではないのです。
4. 発症年齢と発症パターン
パフォーマンス限局型は、一般的な社交不安症とは異なる発症パターンを示すことがあります。特に注目すべきは、成人期以降の発症が珍しくないという点です。「学生時代は平気だった」という方でも、職場での役割変化により症状が顕在化することがあります。
| 発症時期 | 特徴 | きっかけの例 |
|---|---|---|
| 思春期 | 10代半ば~20代前半 | 学校での発表、部活動での実演、口頭試験 |
| 成人期 | 就職後 | 初めてのプレゼン、会議での報告 |
| 中年期 | 昇進後 | 管理職としてのスピーチ、部下指導 |
5. 働く人と大学生におけるあがり症
大学生特有の困難
大学生活では、高校までとは比較にならないほど「人前での発表」の機会が増えます。あがり症を抱える大学生は、以下のような場面で特に苦しんでいます。
- ✔ゼミでの発表・ディスカッション
- ✔卒業論文の発表会
- ✔グループワークでの意見発表
- ✔就職活動での面接やグループディスカッション
「このままでは就職できないかも」という不安から、本来の能力や興味とは関係なく、発表の少ない職種を選んだり、大学院進学を諦めたりするケースもあります。
働く人での特徴
職業によって、あがり症が生活に与える影響は大きく異なります。特に以下のような職業・役割の方は、症状による困難を感じやすい傾向があります:
- ✔ビジネスパーソン: プレゼン、会議での発言、商談
- ✔教育関係者: 授業、保護者対応、研究発表
- ✔医療従事者: カンファレンス、申し送り、学会発表
- ✔管理職: 朝礼、スピーチ、チームマネジメント
また、日本の「失敗が許されない」「皆に迷惑をかけてはいけない」といった文化的背景が、症状を悪化させる要因になっている可能性もあります。
6. 受診の遅れという大きな問題
- ✔社交不安症は発症から初診までに平均10~20年かかるとされ、受診が遅れる傾向があります。
- ✔「病気ではなく性格の問題」という誤解や、困難を悟られないよう対処することで、さらに受診が遅れます。
多くの方が「病気ではなく性格の問題」「恥ずかしがり屋」「準備不足」といった言葉で片付けてしまい、医療相談の対象だと思わない方が非常に多いのが現状です。症状による困難を悟られないよう、無意識のうちに過剰な準備をしたり、発表の機会を避けたり(回避行動)することがあります。
これらの対処は、見合わない労力を強いられたり、自身の評価を下げてしまったり、依存症や肝臓などの病気の問題があり、決してうまくいっているわけではありません。実際の診療では、「学生時代からずっとあがり症で悩んでいた」「もっと早く来ればよかった」という声を非常に多く耳にします。
7. 「あがり症」は治療できます
受診を検討すべきタイミング
以下のような状況にある方は、専門医への相談を検討する価値があります:
□ 発表の数週間前から不安で眠れない
□ 発表のある行事や会議を欠席したことがある
□ あがり症のせいで昇進や転職を諦めた
□ 日常会話は問題ないのに、人前だけで症状が出る
□ 手の震えや声の震えで困っている
□ 「このままでは将来が不安」と感じている
上記のような状況にある方には、認知行動療法や薬物療法などの効果的な治療法があります。
8. まとめ:「あがり症」は治療できる疾患です
パフォーマンス限局型社交不安症、いわゆる重度のあがり症は、決して珍しい疾患ではありません。多くの学生や職業人が密かに同じ悩みを抱えています。「皆は平気なのに自分だけ...」という孤独感を感じる必要はありません。
そして何より、あがり症は適切な治療により改善が期待できる疾患です。認知行動療法や薬物療法など、有効な治療法が確立されています。「性格の問題だから」「あがり症は治らない」と諦める前に、一度専門医に相談されることをお勧めします。
当院では、働く方々や学生の方のあがり症・パフォーマンス不安の治療を行っています。キャリアや学業を諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
参考文献
1) Kessler RC, et al. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 593-602.
2) Ruscio AM, et al. (2008). Social fears and social phobia in the USA: results from the National Comorbidity Survey Replication. Psychological Medicine, 38(1), 15-28.
3) Blöte AW, et al. (2009). Social phobia subtypes in the general population. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 44(11), 878-884.
4) Caballo VE, et al. (2012). Differences in social anxiety between men and women across 18 countries. Personality and Individual Differences, 53(6), 741-746.
5) Wang PS, et al. (2005). Failure and delay in initial treatment contact after first onset of mental disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry, 62(6), 603-613.
6) Olfson M, et al. (2000). Barriers to the treatment of social anxiety. American Journal of Psychiatry, 157(4), 521-527.
江戸川橋ラーナメンタルクリニック
院長 近野祐介
作成日: 2025年10月3日
更新日: 2025年10月3日