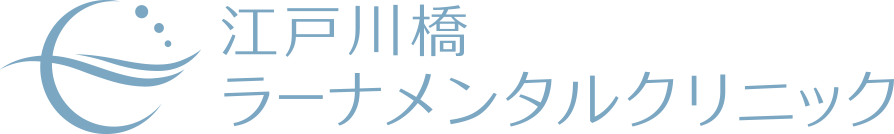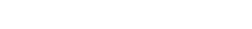冬になると冬眠する?季節性感情障害(冬季うつ病)について知っておきたいこと
1. はじめに
季節性感情障害(SAD: Seasonal Affective Disorder)という病名を聞いたことがありますか?季節に応じて、気分障害が起こる病気で、冬季うつ病もその一つのパターンです。日本ではあまり馴染みがない病名ですが、例えばアメリカでは結構知名度があり、10月(サマータイム切り替えの時期でもあります)には、SNSなどで季節性感情障害に関する情報がかなり見られるようになります。
10月を過ぎ、秋も深まると何が起こるのか?そのメカニズム、治療法を解説します。
2. 季節性感情障害とは
- ✔特定の季節に繰り返しうつ症状や躁症状が現れる気分障害です。
- ✔最も典型的なのは秋から冬にかけてうつ症状が出現し、春になると自然に回復する「冬季うつ病」です。
季節性感情障害は、特定の季節に繰り返しうつ症状が現れる気分障害です。最も典型的なのは、秋から冬(おおむね11月から3月頃)にかけてうつ症状が出現し、春になると自然に回復するというパターンを繰り返すタイプで、これを「冬季うつ病」と呼びます。夏に躁症状が現れたり、夏にうつ症状が現れることもあります。
3. 冬季うつ病に特徴的な症状
- ✔過眠、過食と炭水化物への渇望、体重増加、倦怠感などの非定型的な症状が特徴です。
- ✔診察では「冬は冬眠するようなイメージですか?」という質問に「そうなんです!」という答えが返ってきます。
冬季うつ病は、以下のような非定型的な症状が目立つことが特徴です。
過眠: 夜の睡眠時間が長くなるだけでなく、日中も強い眠気を感じる。
過食と炭水化物への渇望: 特に甘いものやパン、ご飯といった炭水化物を無性に食べたくなる。
体重増加: 過食と活動量の低下により、冬の間に体重が増えやすい。
倦怠感・エネルギーの低下: 体が重く、何をするにも億劫に感じる。
このような症状が見られるため、診察で冬季うつ病を疑って、「冬は冬眠するようなイメージですか?」と尋ねると、「そうなんです!」という答えが返ってきます。また、人によっては「夏服と冬服でサイズが異なる」といったことも起こります。
4. 季節性感情障害の疫学
- ✔地理的な緯度と密接な関係があり、高緯度地域ほど発症リスクが高まります。
- ✔女性患者が男性患者の約4倍と多く、発症のピークは20代から30代です。
季節性感情障害、特に冬季うつ病は、地理的な緯度と密接な関係があることが知られています。研究によれば、緯度が1度上がるごとに有病率が0.14%上昇することが示されており、日照時間の短い高緯度地域ほど発症リスクが高まる傾向があります。一方、夏季のうつ病については、緯度との明確な関連性は認められていません。
性別では、女性患者が男性患者の約4倍と圧倒的に多く、発症のピークは20代から30代の若年成人期に見られます。
アメリカでは数百万人がこの疾患に悩まされているとされ、日本においても潜在的な患者数は少なくないと考えられています。
5. 診断のポイント
- ✔過去2年以上にわたり、特定の季節にうつ病エピソードが発症し、特定の季節に寛解していることが診断基準の一つです。
- ✔「冬は冬眠するイメージになる」ことに困っていたら、一度医療機関への相談を検討してください。
診断基準としては下記のようなものがありますが、あまり難しく考えずに、「冬は冬眠するイメージになる」ことに困っていたら、一度医療機関への相談を検討してみてください。
(参考)季節性感情障害の診断基準
- ✔過去2年以上にわたり、特定の季節(秋・冬)にうつ病エピソードが発症し、特定の季節(春)に寛解している。
- ✔季節性のうつ病エピソードの回数が、非季節性のエピソードの回数を大幅に上回っている。
- ✔季節の変わり目に起こる明らかな心理社会的ストレス(例:年末の多忙など)が症状の原因ではない。
6. なぜ冬に起こるのか:原因とメカニズム
- ✔冬期の日照時間と日照量の減少が深く関係していると考えられています。
- ✔体内時計の乱れとセロトニンの機能低下が主な原因として挙げられます。
季節性感情障害の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、冬期の日照時間の短さに加えて、日照量も深く関係していると考えられています。実際、冬だけでなく曇りの多い梅雨の時期に冬季うつ病の症状がみられる人もいます。
主に以下の2つのメカニズムが有力な仮説として挙げられています。
体内時計(概日リズム)の乱れとメラトニン分泌異常
人間の体には、約24時間周期の「概日リズム(サーカディアンリズム)」、いわゆる体内時計が備わっています。朝の光を目から取り込むことで、この体内時計はリセットされ、同時に睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されます。
しかし、冬になり日照時間が短くなると、特に朝の光を浴びる量が減少し、体内時計が後ろにずれてしまいやすくなります。さらに、朝になっても薄暗い時間が長いため、メラトニンの分泌が十分に抑制されず、日中も通常より高いレベルで分泌が続いてしまいます。
この概日リズムの乱れとメラトニン分泌異常が、過眠、日中の眠気、倦怠感といった症状を引き起こすと考えられています。
セロトニンの機能低下とビタミンD不足
セロトニンは、気分を安定させ、安心感に関わる神経伝達物質です。セロトニンの合成には日光が重要な役割を果たしており、日照時間が減少する冬は、脳内のセロトニンの活動が低下することが研究で示されています。
また、日光を浴びることで体内で生成されるビタミンDも、セロトニンの活性化に関与していると考えられています。冬季の日照不足はビタミンD不足をもたらし、これがセロトニン機能の低下をさらに悪化させる可能性があります。
このセロトニン機能の低下が、気分の落ち込みや、炭水化物を渇望する症状の一因とされています。
7. 治療法について
- ✔光療法が第一選択治療として最も推奨されています。
- ✔薬物療法や認知行動療法も有効とされています。
季節性感情障害は、適切な治療によって症状をコントロールし、つらい季節を乗り切ることが可能です。治療法にはいくつかの選択肢があり、症状の重さや個人の状況に応じて選択されます。
光療法(高照度光療法)
冬季うつ病の第一選択治療として最も推奨されているのが光療法(高照度光照射療法)です。これは、2,500〜10,000ルクス(一般的には10,000ルクス)の明るい光を毎朝30分程度浴びる治療法で、多くの研究でその有効性が示されています。
光療法の効果は比較的早く現れることが多く、1週間以内に症状の改善を実感する方も少なくありません。副作用としては軽度の頭痛や眼精疲労、不眠が報告されることがありますが、一般的には安全性の高い治療法とされています。
治療には専用のライトボックス(光療法機器)を使用します。市販されている製品の中には、十分な光の強度がないものや、適切な距離で使用できないものもあるため、購入の際には医療機関に相談されることをお勧めします。
薬物療法
抗うつ薬による治療も一定の効果があると考えられています。アメリカではブプロピオン徐放錠(日本では未承認)が季節性感情障害の予防に対して米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けており、第一選択になります。日本では第二選択のSSRIが使用されることが多いです。秋に服用を開始し、冬季を通して継続、春に減量・中止するという使い方が一般的です。
心理療法
認知行動療法(CBT)が有効とされています。日本ではあまり一般的ではありませんが、特に季節性感情障害に特化したCBT-SAD(Cognitive Behavioral Therapy for SAD)が有効とされています。この療法では、冬や日照不足に対して抱きがちな否定的な考え方(例:「冬は何も楽しめない」)を見つけ出し、より現実的で柔軟な考え方に変えていく練習をします。また、冬の間も楽しめる活動を計画し、意図的に行動範囲を広げていく「行動活性化」というアプローチも取り入れます。
8. 日常生活でできること
- ✔日光を積極的に浴びる、規則正しい生活リズムを保つことが重要です。
- ✔適度な運動とバランスの取れた食事も症状の改善に役立ちます。
治療と並行して、日常生活の中でも工夫できることがあります。
日光を積極的に浴びる
可能な限り日中に屋外で過ごす時間を作り、自然光を浴びましょう。曇りの日でも屋外の明るさは室内より格段に明るく、効果が期待できます。室内では窓際で過ごす時間を増やし、カーテンを開けて自然光を取り入れることも有効です。
規則正しい生活リズム
毎日同じ時間に起き、同じ時間に寝ることで、体内時計のリズムを整えやすくなります。
適度な運動
冬でも無理のない範囲で体を動かす習慣を持つことが推奨されます。
バランスの取れた食事
炭水化物への欲求が強くなりがちですが、栄養バランスの取れた食事を心がけることが大切です。
9. まとめ
季節性感情障害は、日照時間と日照量の変化という要因で起こる病気です。
もし毎年秋から冬にかけて気分の落ち込みや意欲低下が続き、日常生活に支障が出ているようであれば、ぜひ一度医療機関にご相談ください。早期に適切な対処を始めることで、冬の時期もより快適に過ごせるようになる可能性があります。
症状には個人差があり、治療法の選択も一人ひとり異なります。医師とよく相談しながら、ご自身に合った対処法を見つけていただければと思います。
江戸川橋ラーナメンタルクリニック
院長 近野祐介
作成日: 2025年10月12日
更新日: 2025年10月12日