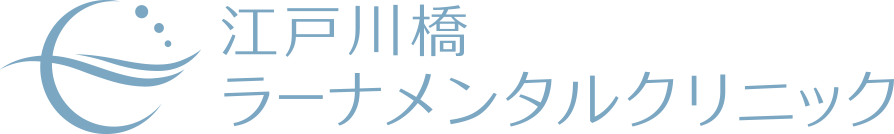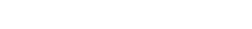- 記事の要点
- 強迫症(強迫性障害)とは
- 強迫症(強迫性障害)の主な症状と特徴
- 強迫症(強迫性障害)の原因として考えられていること
- 強迫症(強迫性障害)はどのくらいの人が経験するのか
- 強迫症(強迫性障害)の診断
- 強迫症(強迫性障害)の治療
- よくある質問(Q&A)
- 強迫症(強迫性障害)のまとめ
記事の要点
- 強迫症は「強迫観念」と「強迫行為」を繰り返す疾患で、日常生活に支障をきたすほど症状が過剰になることが特徴です。
- 生涯有病率は約2~3%と決して珍しくなく、薬物療法と認知行動療法(特に暴露療法)により改善が期待できます。
- 「我慢すればいい」と放置すると症状は悪化する傾向があるため、早期の受診と治療開始が大切です。
Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) は強迫性障害と訳されていましたが、最近は強迫症と訳されています。ここでは強迫症とし、見出しでは強迫症(強迫性障害)とします。
強迫症(強迫性障害)とは
強迫症は、不安を引き起こす「強迫観念」と、その不安を和らげるための「強迫行為」を繰り返してしまう精神疾患です。主な症状には、汚染への恐怖、加害恐怖、確認行為、儀式的な行為などがあります。
「手を何度も洗ってしまう」「鍵をかけたか何度も確認する」といった行動は、誰にでも経験があるかもしれません。しかし、強迫症の場合、これらの行動が日常生活に大きな支障をきたすほど過剰になり、自分でもやめたいと思いながらもコントロールできなくなってしまうのです。強迫症は、症状が出ても我慢して受診するまでに長い時間がかかってしまうことが多い病気です。もしも、強迫症ではないかと思った場合は、早めに医療機関に相談することをおすすめします。
強迫症(強迫性障害)の
主な症状と特徴
強迫症の症状は、大きく「強迫観念」と「強迫行為(強迫症状)」の2つに分けられます。強迫観念とは、自分でも不合理だと分かっていながら、頭から離れない不安や考えのことです。
強迫観念には、以下のようなものがあります。
これらの強迫観念は、ご本人にとって非常に現実味を帯びて感じられ、強い不安や恐怖、不快感を引き起こします。
汚染・不潔への恐怖
自分や自分の持ち物、周囲の環境が細菌やウイルス、化学物質、汚れなどで汚染されているのではないかという強い不安。例えば、「ドアノブを触ったら病気になるかもしれない」「他人のくしゃみで汚染されたかもしれない」といった考えが浮かびます。
加害恐怖
自分の不注意や意図しない行動によって、誰かを傷つけたり、危害を加えてしまうのではないかという恐怖。例えば、「運転中に人を轢いてしまったのではないか」「刃物で家族を傷つけてしまうのではないか」といった考えに苦しみます。
確認強迫に関連する疑念
「鍵を閉め忘れたのではないか」「ガス栓を閉め忘れたのではないか」「大切なものを捨ててしまったのではないか」など、何かをやり忘れたり、間違ったことをしたりしたのではないかという執拗な疑念。
対称性や正確性へのこだわり
物事が特定の手順で、あるいは完璧な順序や配置で行われないと気が済まない、強い不快感を感じる状態。例えば、物が左右対称に置かれていないと落ち着かない、書類の文字が少しでもずれていると許せない、などです。
宗教的・道徳的なこだわり
不道徳な考えや冒涜的な考えが頭に浮かび、罪悪感に苛まれること。
その他
特定の数字や言葉、色などに不吉な意味を感じたり、何かを集め続けたり(ためこみ症とは区別されます)、特定の身体的愁訴にとらわれたりすることもあります。
また、これらの不安を打ち消すために行うのが強迫行為です。強迫行為には、以下のようなものがあります。
洗浄・清掃
 手を何度も長時間洗う、シャワーを何度も浴びる、家の中や特定の場所を執拗に掃除する、など。
手を何度も長時間洗う、シャワーを何度も浴びる、家の中や特定の場所を執拗に掃除する、など。
確認行為
 家の鍵やガス栓、電気のスイッチなどを何度も確認する、手紙やメールの宛先を何度も確認する、など。
家の鍵やガス栓、電気のスイッチなどを何度も確認する、手紙やメールの宛先を何度も確認する、など。
儀式的な行為
特定の順序で物事を行わないと気が済まない、特定の言葉を心の中で繰り返す、特定の回数だけ行動を繰り返す、など。
対称性や正確性を求める行為
物を完璧な位置に並べ直す、左右対称になるように整える、など。
回避
不安を引き起こす状況や場所、物、人を避ける行動。例えば、汚いと感じる場所に行かない、特定の人との接触を避ける、など。
精神的な儀式
心の中で特定の言葉を唱えたり、特定のイメージを思い浮かべたりすることで不安を打ち消そうとすること。
強迫行為は一時的に不安を軽減させる効果があるかもしれませんが、根本的な解決にはならず、むしろ強迫観念を強化し、症状を悪化させる悪循環に陥ることが多いです。
これらの行為は、最初は短時間でいても、次第にエスカレートし、1日に何時間も費やすようになることがあります。強迫症状に時間を取られることで、仕事や学業、家事などの日常生活に支障をきたし、人間関係にも影響を与えることがあります。また、身体的な影響としては、過度の手洗いによる手荒れ、長時間の確認行為による疲労、睡眠不足などが見られます。「これは普通のことで、受診するようなことではないのでは?」「ちょっと我慢すればいいだけでは?」と思われるかもしれませんが、実は我慢しているとどんどん症状が悪化していく傾向があります。
強迫症(強迫性障害)の
原因として
考えられていること
強迫症の原因は、単一の要因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。生物学的要因としては、脳内の神経伝達物質、特にセロトニンのバランスの乱れが関与していることが分かっています。また、遺伝的な要素もあり、家族に強迫症の方がいる場合、発症リスクがやや高くなることが知られています。
心理的要因としては、完璧主義的な性格傾向や、不確実さへの耐性の低さ、責任感の強さなどが関連していると言われています。しかし、これらの性格特性を持つすべての人が強迫症になるわけではありません。
環境的・社会的要因も重要です。大きなストレスや生活環境の変化などが引き金となることがあります。重要なのは、強迫症は「心が弱いから」「意志が弱いから」なるものではないということです。
強迫症(強迫性障害)は
どのくらいの人が
経験するのか
強迫症は決して珍しい疾患ではありません。日本を含む世界各国の調査によると、生涯有病率は約2~3%とされています。つまり、100人に2~3人は人生のどこかで強迫症を経験する可能性があるということです。これは、学校のクラスや職場の部署に1人はいてもおかしくない割合です。
発症年齢は幅広いですが、多くの場合、10代後半から20代前半に発症することが多く、30歳までに約90%の方が発症すると言われています。強迫症の発症に大きな性差はないとされていますが、小児期の発症では男児にやや多く、成人期では女性にやや多いという報告もあります。この背景には、生物学的な要因だけでなく、社会文化的な要因や受診行動の違いなどが影響している可能性も考えられますが、明確な理由はまだ分かっていません。
強迫症(強迫性障害)の診断
強迫症の診断は、精神科医や心療内科医などの専門医によって行われます。診断には国際的な診断基準が用いられており、主にDSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)やICD-11(国際疾病分類第11版)の基準に基づいて判断されます。
DSM-5-TRの診断基準
ここでは、DSM-5-TRにおける強迫症の診断基準の概要をご紹介します。
- 強迫観念、強迫行為、またはその両方の存在
強迫観念は以下の(1)と(2)によって定義される- 反復的かつ持続的な思考、衝動、またはイメージで、それは侵入的で不適切なものとして体験され、著しい不安や苦痛の原因となる。
- その人は、その思考、衝動、またはイメージを無視したり抑え込もうとしたり、または何か他の思考や行動(すなわち、強迫行為を行うことによって)で中和しようと試みる。
強迫行為は以下の(1)と(2)によって定義される
- 反復的な行動(例:手を洗う、順番に並べる、確認する)または心の中の行為(例:祈る、数を数える、言葉を静かに繰り返す)であり、その人は強迫観念に反応して、または厳格に適用しなければならない規則に従って、それらの行為を行うように駆り立てられていると感じている。
- その行動または心の中の行為は、不安または苦痛を予防したり緩和したりすること、または何か恐ろしい出来事や状況を予防することを目的としている。しかし、これらの行動または心の中の行為は、それらが中和したり予防したりするように設計されている対象とは現実的な関連がないか、または明らかに過剰である。
- 強迫観念または強迫行為は時間を浪費させる(例:1日に1時間以上かかる)、または臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
- その強迫症状は、物質(例:乱用薬物、医薬品)または他の医学的状態の直接的な生理学的作用によるものではない。
- その障害は、他の精神疾患の症状ではうまく説明されない。(例:全般不安症における過剰な心配、醜形恐怖症における外見へのとらわれ、ためこみ症におけるためこみ、抜毛症における抜毛、皮膚むしり症における皮膚むしり、常同運動症における常同運動、摂食障害における儀式的摂食行動、物質関連障害群および嗜癖性障害群における物質使用への渇望、病気不安症における病気へのとらわれ、パラフィリア障害群における性的空想や衝動、秩序破壊的・衝動制御・素行症群における衝動、うつ病における反復的思考、統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群における妄想や奇妙な思考)
診断プロセスでは、まず詳しい問診が行われます。症状の内容、頻度、日常生活への影響などについて、医師が丁寧に聞き取ります。また、Y-BOCS(イェール・ブラウン強迫尺度)などの心理検査を用いて、症状の重症度を評価することもあります。
他の精神疾患(うつ病、不安障害など)や身体疾患との鑑別も重要です。強迫症状は他の疾患でも見られることがあるため、専門的な判断が必要となります。インターネットの情報だけで自己判断することは危険です。「もしかして」と思ったら、まずは医療機関に相談することが、適切な治療への第一歩となります。
強迫症(強迫性障害)の治療
強迫症の治療目標は、強迫症状を軽減・消失させ、さらには再発予防を行い、日常生活の質(QOL)を向上させることです。治療法は大きく分けて、薬物療法と精神療法(心理療法)があり、多くの場合、これらを組み合わせて行われます。
薬物療法
薬物療法では、主にSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)という種類の抗うつ薬が使用されます。これらの薬は、脳内のセロトニンという神経伝達物質のバランスを整えることで、強迫症状を軽減する効果があります。効果が現れるまでに1~3か月かかることが多く、継続的な服用が重要です。副作用として、服用開始時に吐き気や眠気などが現れることがありますが、多くの場合、時間とともに軽減します。医師と相談しながら、自分に合った薬を見つけていくことが大切です。
精神療法
精神療法では、認知行動療法(CBT)、特に「暴露反応妨害法(暴露療法)」が効果的とされています。これは、あえて不安を引き起こす状況に身を置き(暴露)、強迫行為を行わないようにする(反応妨害)という方法です。例えば、汚れが気になる方なら、少しずつ「汚い」と感じるものに触れ、手を洗わない時間を延ばしていきます。最初は不安が強くなりますが、繰り返すうちに不安は自然に下がっていき、強迫行為をしなくても大丈夫だということを体験的に学んでいきます。
生活改善とセルフケア
 治療と並行して、規則正しい生活リズムを整えること、十分な睡眠をとること、適度な運動を行うことも重要です。ストレスは症状を悪化させる要因となるため、リラクゼーション法やマインドフルネスなどのストレス対処法を身につけることも有効です。また、家族や周囲の理解とサポートも回復の大きな力となります。
治療と並行して、規則正しい生活リズムを整えること、十分な睡眠をとること、適度な運動を行うことも重要です。ストレスは症状を悪化させる要因となるため、リラクゼーション法やマインドフルネスなどのストレス対処法を身につけることも有効です。また、家族や周囲の理解とサポートも回復の大きな力となります。
治療期間は個人差が大きく、数か月で改善する方もいれば、数年かかる方もいます。焦らず、自分のペースで治療に取り組むことが大切です。
よくある質問(Q&A)
強迫症(強迫性障害)の
まとめ
ここまで強迫症について詳しく見てきました。強迫症は、適切な治療により改善が期待できる疾患です。「我慢すればいい」「時間が解決してくれる」と考えがちですが、実際には症状は徐々に悪化し、生活への影響も大きくなっていきます。早期に治療を開始することで、症状の改善も早く、より良い予後が期待できます。
受診をためらう気持ちはよく分かります。「こんなことで病院に行っていいのか」「恥ずかしい」「変だと思われないか」といった不安があるかもしれません。しかし、症状に悩んでいるなら、それは十分に受診の理由になります。それぞれに合った最善の治療法を一緒に考え、安心して治療に取り組めるようサポートします。一人で悩まず、専門家の力を借りて、回復への第一歩を踏み出してみませんか。